Vol.3
←最新ブックレビューへ戻る
| ●Vol.4 No31〜 ●Vol.3 No21〜No30 ●Vol.2 No11〜No20 ●Vol.1 No 1 〜No10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 の 話 題 |
No30(2003/4/7) 思えば誰に頼まれたのでもなく、どうして、ほとんどの人が興味を持たないであろうノルウェーの本などを紹介し続けてきたのだろう?Mmmm ...と珍しく、このホームページの存在意義に疑問を感じました(最近では、全然更新しなくてホームページを持っていたことすら忘れているようですね、はい)。 そこで4月。春です。 何か新しいことを始めたいみなさんのために、本屋にはたくさんの語学テキストが並んでいます。毎年4月号だけ買って挫折している皆さん、今回は少し「有益な」情報提供をいたしましょう!ノルウェー語の語学書紹介ですよ。 (あまり関係ないけど、なんでNHKの語学番組は、女性アイドル路線になってしまったのでしょう?語学を習うのは女性が多いから、美少年系をアシスタントに使った方がいいと思うんですけどね。。。もし世界が一変して、ノルウェー語講座がテレビでO.A.されるようになったら、誰がアシスタントにいいかな〜と妄想はふくらみます) 今回のご協力は、本欄でも何度か紹介しているノルウェーの書店「Norli」さん。新しい語学書のパンフレットを頂きました。Takk ! なお、語学書の多くは教科書(tekstbok)以外に、問題集(arbeidsbok)、CDやカセット(kassetter)が用意されているが、別売。このリストの値段は、tekstbokのものです。
なお筆者は、初の語学書出版に向け、現在「鋭意校正中」(かっこ悪いな〜)。 本当は2002年12月出版予定が4月に延び、今の段階ではいつになるか断言できませ〜ん。でも、必ず出版にこぎつけますので、待っていて下さい! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 の 話 題 |
No29(2002/12/1) 早いもので、もう師走。 恒例の年末行事、「Årets bøker2002」を紹介する時期になりました!今年一年、いったいどんな本が出版されたのかを、チェックするのは、ドキドキしますね〜(してるの筆者だけ?)。 昨年の例にならって、カタログの中から、面白そうな本、変わり本などをリストアップしましょう。
いかがでしょう?少しは、触手が伸びる本がございましたでしょうか? 「もっと、まともな本を紹介しろ!」という声が、ノルウェー出版界から聞こえてきそうですね、はい。 来年まで、ごきげんよう〜♪ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 の 話 題 |
No28(2002/10/2) ノルウェーの新聞を、あらためて日本の新聞の常識で見なおすと、気づくことがあります。 書評欄は、週一回(日曜日)が常識の日本の新聞からすると、ノルウェーの新聞には、もっと多くの回数、書評や作家インタビューが載っています。 また、人口が少ない国の長所(?)として、「競争が少ない」があると思いますが、これは書評にも当てはまるでしょう。 日本の一般紙の書評欄に掲載されることに比べて、ノルウェーの新聞の方が、ぐっと「広き門」だな〜と感じますね。 しか〜し、たくさん掲載してもらえるからと言って、ノルウェーの作家が甘やかされているとは限りません! インタビューに大きく紙面を割いてもらい、新作について熱く語っても、その横に掲載されている自作の書評には、結構、シビアな批評が目につくこともあるのです。とほほ。 「普通、インタビュー載っけてくれたら、けなさないよね?」なんていう期待は通じないのだな。 ...とあらためて感じたのが、8月15日付のアフテンポステン紙。 ここ何年かで、すっかりノルウェー若手作家を代表するハンネ・ウシュタヴィク(Hanne Ørstavik)のインタビュー記事と、新作「43週」(「Uke 43」)の書評の切り抜きをもらった時でした。 トレードマークだったスキンヘッド(または一分刈り)から、髪が伸び、のこやかに笑う彼女を写した大きなカラー写真。 過去における彼女のインタビューと同じように、誠実に語り、答えています。 インタビューの中で、「私は、この新作で新たに自分の作家性を切り開き、新しい方向性を見つけたと思う」。 「最良の小説とは、読者に、実存的、感情的、思考的、あらゆるレベルで体験できる空間を創ること」など、真面目に語っています。 「よくわかんないけど、この本もとりあえず(読まないかもしれないけど)買ってみよう!」と、思う筆者(単純?)。 そのすぐ横には、インタビュアーとは別の人の筆(Cathrine Sandnes)による、ウシュタヴィクの新作「43週」の書評が載っています。こっちも読んでみましょう。 「前の3作の方が、良かった」(え??) 「主人公の人間像が、はっきりしない」(きっつい!) など、私が作者ならば泣きそうな批評の言葉...。もちろん、誉めている箇所もあるのですが、全体的に、否定的な言葉ばかり記憶に残るのはなぜ? 「これを目にした作者は、紙面を破きたくなるのでは?」と、遠い日本から心配しました。 だって、自分の語った言葉を、すぐ横からツッコミ入れられたようなもんですよ、これは。 でも、このパターン珍しくないのも事実です。過去の書評、他紙も含めて思い出すと、ありました、ありました。 作家が一生懸命、自作や作家とは、なんて語っている横にある厳しい批評。う〜ん、そんなことするから、ますます「作家」の性格がゆがんでしまう...。表現者も楽ではありません。 「批評の健全性」 「なれ合いを禁じる」 「緊張感を保つ」 といった観点からすれば、ノルウェー式は正しいですよね。 「新聞に掲載してもらうチャンスは大きい」でも 「けなされるの覚悟」...。 そういえば、「切磋琢磨」という言葉がありましたね。ノルウェー語にもあったかな? その他、この書評を読んで気になった点が一つ。 彼女の出版社が、変わってしまったようです。以前は、Oktober(「10月」の意味)社だったのですが、新作は親会社のAschehoug社から出版されています。さびしい...。 ノルウェーの出版社は、大手の寡占化が進んでいるので、同じ本が今は違う出版社から出ている、ということもあります。 ユニークな中小出版社が、大手の傘下になってしまうのは反対です! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 & カ セ ッ ト ブ ッ ク |
No27(2002/5/12) せっかくノルウェーで買った本が、「積読」状態になっている、なんてことありませんか? ...少なくとも私はそうです。毎年、ノルウェーに行っては「これも、あれも」と本を買い込み、わざわざ別便で送ったのに、肝心の本が届いた頃には、すっかり興味をなくし、1ページ目で挫折した本は、数知れず...。 「ま、いっか、老後の楽しみに取っておこう」スタンスになっちゃってますが、果たして老後にノルウェー語、覚えてるんでしょうかね〜? ビョルグ・ヴィーク(Bjørg Vik)の「サンクト・ハンスハウゲンのポプラ」(Poplene på St. Hanshaugen)は、そうした「マイ積読コレクション」の1冊でした〜。 ヴィークは、ノルウェーの現代ノルウェー文学を作家を代表する女性作家です。彼女の作品の特徴は、いろいろありますが、「読みやすい、簡単で短い文章」もその1つです。 友達からもらったこの本を、ぱらぱらめくっては、「読みやすそう〜」と思い、そのうち読もうと本棚に並べてはや4年の月日が流れました...(ゆっくり熟成中)。 きっと去年のクリスマスプレゼントがなければ、この本は「マイ老後コレクション」入りしていたでしょう。 私の無言の願いを聞き入れたサンタさんが、私に「サンクト・ハンスハウゲンのポプラ」のカセットブックを贈ってくれたのです!(うそ、友達が偶然、贈ってくれたのです!) カセットブック、またはCDブックは、ノルウェーの本屋さんにかなりの数が並んでいます。 私もずーーーと何か欲しかったのですが、いかんせん、とても高くて手が出ませんでした。 プレゼントという形で入手したカセットブックは、全部で7カセット。本自体はポケットブック版で300ページ強ですから、かなりボリュームがあります。 今まで1ページしか読めなかった本ですが、カセットブックのおかげで、すぐ第1章が読み(聞き?)終わりました。 読み手は、国立劇場の女優ですが、聞いててほれぼれするほど、きれいなノルウェー語!聞きながら、「あ〜、こんなにきれいに発音とイントネーションがつけられてうらやましい〜、けっ、あたいには一生無理だよ!」と、ノルウェー人を妬んでどうする!! さて、カセットブックを聞きながらだと、すいすいページも進みましたが、予想以上に物語が面白かったため、カセットのスピードにしびれをきかせ、ついにカセットなしに普通の読書モードへ(カセットブックさん、ごめんなさい)。 物語は、50年代のオスロ、サンクト・ハンスハウゲン辺りの一帯が舞台です。主人公の女の子、エルシーの家族、友達、さまざまな恋愛風景と、当時のオスロの風俗、文化が楽しめる作品です。 実在する地名、特に通りの名前がたくさん出てきます。ですから、その辺りを知っている人には、もっと楽しめる作品と言えるでしょう。 まだ、あまり豊かでなかったノルウェー人の暮らし、妊娠してしまったら即結婚だった風潮、たくさんのダンスパーティと壁の花の女の子たち、などなど。決してドラマティックでない物語なのに、どうしてこんなに引き込まれてしまうのか、不思議な本でした。 途中からカセットは外してしまいましたけど、いわば読書の助走をつけてくれたのが、カセットブックと言えます。また、発音のお手本のようなカセットブックは、ノルウェー語勉強中の方にもお薦めでしょう。 今年のクリスマスも、カセットブック欲しい〜、と願うケチな筆者でした! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 ・ 映 画 の 話 題 |
No26(2002/3/2) すっかり更新をさぼってしまいまして恐縮です。おまけに今日、紹介しようと思っている話題は、ちょっとタイムラグがあったりして、全然、「最新」ではありません。「スローフード」ならぬ、「スローアップデート」路線で参りましょう! ・アストリッド・リンドグレーンとノルウェーの作家たち スウェーデンの国民的作家アストリッド・リンドグレーン(Astrid Lindgren)の死は、日本でも大きく報道されましたが、同じ北欧つながりのノルウェーでも、彼女の死を悼む記事がたくさん書かれました。 ダーグブラーデ紙(2002年1月29日)には、ノルウェーの作家たちに「あなたにとって、アストリッド・リンドグレーンはどんな意味を持っていましたか?」というアンケートを行った回答が寄せられています。幾つか紹介しましょう。 まず、「ノルウェーのおばあちゃん」こと、児童文学作家のアンネ・カト・ヴェストリー(Anne.Cath.Vestly)のコメントから。 「リンドグレーンの具合がとても悪いことは聞いていました。彼女がノーベル文学賞をもらえなかったのは、とても変だと思います。彼女がもらうことを、ずっと望んでいたのだけど...。彼女の本が、たくさんの国でこれからも長く生き続けることを喜んでいます。 私のお気に入りの本は、特に”ミオ、私のミオ”。彼女は、ユーモアと冒険心と共に、多くの悲しみと寂しさがこの本には込められていると思います。私は、大人になってからはじめて、彼女の本を読みました。というのも、他の児童文学を読むのに慎重だったから。影響を受けるのがこわかったのね。結局、彼女とは一度も挨拶したことなかったです」。 二人が一度も面識がなかったとは、ずいぶん、意外で驚きました!ちなみにヴェストリーの作品については、私の講演録(町田)の中で触れています。 次は、この欄でおなじみの若手作家、アーレン・ロー(Erlend Lo)のコメントより。 「僕が小さかった時、両親はよくアストリッド・リンドグレーンの作品を読んでくれた。彼女は、僕にとって、とても大きな意味を持っている。今、大人になって、彼女がどれだけ新しいものを生み出してきたか、理解できるようになったよ。 ちょっと前、僕は彼女がノーベル文学賞をもらうべきだ、と公の席で言ったんだ。というのも、彼女にノーベル文学賞を与えないならば、他の児童文学にこの賞が与えられる可能性はゼロだからね。いくら、児童文学の功績がすばらしくても、正当に評価されていない表れではないだろうか?」 確かに、ローの小説「ナイーブ・スーパー」(Naiv Super)の中には、主人公が尊敬できる人物として、「アストリッド・リンドグレーン」をリストに挙げているシーンがありました。 お次は、SF作家・児童文学作家・純文学作家のトゥール・オーゲ・ブリングスヴァール(Tor Åge Bringsværd)のコメントです。 「たとえ彼女が死んでしまったとしても、彼女の作品は、私たちの心にいつまでも残り続けるだろう。読者としての立場では、彼女の書いたものほとんど全てに感謝している。作家としての立場では、リンドグレーン(とトーベ・ヤンソン)は、世代間の掛け橋を築くことは可能だ、と私に教えてくれたことを感謝しています」。 最後に、やはりこの欄でおなじみのリン・ウルマン(Linn Ullmann)のコメントで締めくくりましょう。 「アストリッド・リンドグレーンは、まず第一に、文学にとって、はかりしれない大きな意味を持っています。彼女は、児童文学でも、大人向けの文学でも、新境地を開きました。 もし、彼女がいなければ、私は本を読むことも、書くことも、考えることもしなかったでしょう。リンドグレーンの本は、私の人生の一部です」。 ・ベルリン映画祭で話題を呼んだノルウェーの異色映画 今年のベルリン映画祭は、日本の宮崎アニメが金熊賞を取り、日本で話題になりました(「千と千尋の神隠し」は、ノルウェー語タイトルが「Borte med åndevinden」になってて感心)。が、ノルウェーのメディアでは、この作品よりも、ノルウェーから出品された異色のドキュメンタリー映画に話題が集中しました。 映画のタイトルは、「オール アバウト マイ ファーザー」(Alt om min far)。はて、どこかで聞いたことがあるような...、そうです、スペインの巨匠ペドロ・アルモドバル監督の映画「オール アバウト マイ マザー」(Alt om min mor)というのがありましたよね。 あの映画では、盲目的ともいえる無心な母性愛が語られていましたが、ではこの「オール アバウト マイ ファーザー」は、すばらしい父性愛を描いているのか、というとかなり違うみたいです。 ダクスアヴィーセン紙(2002年2月14日)が、本映画の特集を組んでいます。まず、映画を理解するための基礎的データーをご紹介しみましょう。かなり、ややこしいです。 この「オール アバウト マイ ファーザー」の主人公は、ノルウェー国内ではとても有名な医師、エスベン・ベーネスター(Esben Benestad)ですが、彼にはもう1つの女性名エスベン・エステル・ピレッリ・ベーネスターEsben "Esther Pirelli "Benestadの方で知られています。 彼は、英語でいうところのtransvestite(ノルウェー語では、transvestitt)、つまり女性の服装をしたり、メークをする欲求がありますが、男性の装いをする時もあります。ただ誤解しやすいのは、こうした嗜好があっても、彼はへテロであり、2度の結婚相手は女性で、現在の妻は同じく医師のエルサ・アルモースです。 二人は南ノルウェーで、診療所を持ち、また共著もあります。昨年、「揺れ動く性」(Kjønn i bevegelse)という学術書を出版し、その中で、従来からある男性・女性という認識以外の多様なセクシュアリティー、つまり、異性愛、トランスジェンダー、トランスセクシャル、半陰陽などを医学的に解説しました。 昨年夏のオスロ滞在中、本書について語るレクチャーが、書店Norliで催されたので参加しました。男性のエスペンさんは、その時は、エステル・ピレッリさんの装いで、ユーモアたっぷりの人柄がしのばれました。写真は、その時のものです。  で、今回の映画の監督は、彼の息子、エーヴェン・ベーネスター(Even Benestad)です。監督は、自分の父親であるエスベンと父親のもう一つの人格、エステル・ぺリッレについて映画にしています。 で、今回の映画の監督は、彼の息子、エーヴェン・ベーネスター(Even Benestad)です。監督は、自分の父親であるエスベンと父親のもう一つの人格、エステル・ぺリッレについて映画にしています。男性が女装する映画というのは、アメリカのコメディー映画などでもおなじみですが、本映画は、笑いを取るために、父親の女装を利用しているのではないそうです。 むしろ、監督自身と父親との関係、さらに女性として装いたい欲求を持つ父親と家族の関係についてを描いた作品とのこと。 ただ、現在のエスベンの妻、エルサは、彼の嗜好性を理解していますが、エスペンの前妻で監督エーヴェンの母親は、映画の中で、初めて自分の夫の違う面を発見した時の驚きを語っています。 さらに、監督の妹と、継母であるエルサの難しい関係なども、映画の中で取り上げられているそうです。複雑でしょうね。。。 ベルリン映画祭出品のため、父と息子はベルリンを訪れました。映画自体は、観客の評判もかなり良かったそうです。 さらに金熊賞は逃しましたが、ベルリン映画祭の1セクションである「テディー賞」が贈られました。 この賞は、同性愛やトランスジェンダー・セクシャルをテーマとした作品を対象に贈られる特別な賞ということ。父と息子の喜びの様子が、報道されています。 2月末よりノルウェー国内で上映が始まり、興行成績は順調のようです。 日本でも、上映されるといいですね....少なくとも、「オール アバウト マイ マザー」より面白そうです。 ・おまけ 拙著「私のノルウェー留学」をお読みいただいた方は、覚えているでしょうか? 私が留学中に書いた論文(という名の作文)が、大学内の雑誌NOAに掲載してもらえるハズなのに、なかなか肝心の雑誌が発行されなかったエピソードを....。 とうとう、今年の1月になって、オスロ大学の先生より送られてきました。タイトルは、「ノルウェー語から日本語に翻訳する場合の問題点−”ヘッダ・ガブラー”に見る人称代名詞の使用」です(このタイトル聞いただけで、おもしろそう!っと言ってくれる方は、果たして何人?)。 何かの用事で、オスロ大学に行かれる方は、構内の本屋さん「アカデミカ」に売っているかもしれませんので、どうぞ、お手に取ってくださいませ。書いてからすでに2年近くが流れました...Typisk norsk! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 の 話 題 |
No25(11/20) 今年も、ノルウェーの本屋さん「Norli」から、今年出版された本のカタログ、「Årets bøker2001」が届きました。 これが届くと、「あ〜年末なんだな〜」と感慨深いものがあります(No.4では、昨年のカタログを取り上げています)。 この欄では、比較的、純文学の小説を取り上げていますので、今回は、なるべくそれ以外のジャンルを、カタログからピックアップしました。なお、値段はノルウェークローネ表示です(1クローネはおよそ14〜15円)。 NB! シャレで選んでいるものがありますので、中味の保証はありません!
リストにもれたジャンルで目立つものといえば、「ゴルフ」本でしょう。ゴルフ人口が増え続けるノルウェーを反映して、翻訳もののガイドブックが、何冊か出版されています。 ノルウェー人とゴルフ − しっくりしないと思うんですけど、お金ができると人間やることは、一緒でしょうか。 他に活況を呈しているジャンルは、何といっても「料理本」。本屋では、かなりの面積を占めています。昔ながらの、料理の作り方が生真面目に載っているものから、人気者のシェフに焦点を当てた本も出版されてます。 イギリスのTV番組「The naked chef」は、Jamie Oliverという若い兄ちゃんが、ワイルドに料理を作る姿を映した番組ですが、ノルウェーでも放送され、関連本「Mat fra Jamies kjøkken」(Food from Jamie's kitchen)が,翻訳出版されてます。さしずめ、イギリス版「ビストロスマップ」でしょうか?(ビジュアル重視ということで) イギリスからの本ということで言えば、「ハリー・ポッター」シリーズが、ノルウェーでも大人気。4冊セットが790クローネで販売されてます。子供がゲームをやめて、本を読んでくれるなら、と買ってあげる親が多いのでは? さて、ノルウェーの本に興味はあっても、買い方がわからない方!私の本購入法を、紹介しますので参考にしてみては、いかがでしょうか? 「夢ネット」からリンクでつながっている書店「Norli」(http://www.norli.no/index.html)へ、いつもメール注文しています。 e-mailアドレスは、eksport@norli.no 英語のメールでOKです。メールには、注文したい本のタイトル(わかれば、著者名と出版社も)と希望冊数、自分の住所と名前を記します。支払方法は、カードが簡単。VisaやAmexなどが使えます。カードの番号と有効期限をあわせて記入します。 大体、メール送付後、10日後から2週間ほどで本とカードの伝票が届きます。簡単ですよね?Prøv! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 の 話 題 |
No24(11/10) 「いや〜、読書の秋、いいですね〜」とまったりしているうちに、ノルウェーはすっかり「冬モードに」入ってしまったようで、焦ってます。 今年の秋、ノルウェーの出版界は活況を呈したようです。人気作家・大物作家の新刊ラッシュが続き、市場は小さいながらも、新聞を見ると充実した様子がうかがえますね。 今日は、その中から2冊を取り上げましょう。何度かこの欄に登場しているアーレン・ロー(Erlend Loe) と、やはり登場済みのリン・ウルマン(Linn Ullmann)の新作についてです。(が、怠け者&吝嗇な筆者は、まだ2冊とも買って読んでません。来年くらいには、ポケットサイズ版で出ると思うので、安くなってから買おうと思ってます)。 まず、スキンヘッド兄ちゃんこと、アーレン・ロー(彼はファッション性スキンヘッドそれとも、必然性スキンヘッド?)からです。タイトルは、「フィンランドについての事実」("Fakta om Finland", Cappelen社)。 作家自身、このタイトルはお気に入りのようで、アフテンポステン紙のインタビュー(2001年10月10日)中、「このタイトル気に入ってるんだ。教科書みたいな無味乾燥で退屈なタイトルだろ?」と、自信たっぷり。本の装丁も、タイトルに合わせたごくシンプルなもので、学術書と見まがうつくりになってます。 主人公の男性は、カタログやパンフレットを作る作家。フィンランドについて何も知らない彼ですが、フィンランド大使館より「ノルウェーの観光客向けにフィンランドのカタログを作って欲しい」と仕事をもらいます。彼がパンフレットを作るに当たって参考にしたのは、1981年8月号のナショナル・ジオグラフィック誌と、1976年デンマークで発行された旅行のガイドブック。当時の大統領の名前を、そのまま引用しちゃったりと、ひどいパンフレットですが、フィンランドについてあまり知らないノルウェー人にとっては、どうでもいいことです。 作家は、同インタビューの中で、ノルウェー人のステレオタイプなフィンランド像(大酒飲み、サウナなど)に言及しています。近いようでも案外、フィンランドのことって知らないものなのですね。 そんなステレオタイプなイメージとして、やはり「森と湖の国フィンランド」があります。この湖(水)と主人公の相性は良くありません。あふれでる水、コントロールできない水、そして変化の象徴として、彼は、湖(水)を恐れています。 アフテンポステン紙の書評(2001年10月10日)によると、この本は、たくさんの出来事がドラマティックに起きる小説ではありません。パンフレットつくり、彼と若い女性の出会い、ネオナチのグループに入ってしまっている彼女の弟、グループからの弟の救出劇など。ちなみにハッピーエンドだそうです。 本書に関しては、おおむね批評は好意的でした。特にダーグブラーデ紙の書評(著名な文芸評論家、Øystein Rottem)は絶賛に近い批評を書いていますが(2001年10月9日)、ローの持ち味である鋭いアイロニーとユーモアを保ちながら、今までにない深みがあるとのこと。 一方、アフテンポステン紙の書評では、構成力や叙述など、技術面では今までのベストとしながら、内容的にはやや退屈であると指摘しています。 2つの書評で一致しているのは、ローの文体の変化に触れていること。今までの、ミニマリスティックな短く歯切れの良い文体から、より長い文章での表現法へ変化があったそうです。これは、読むのが楽しみです。 ではお次は、リン・ウルマンに移りましょう。 9月、互いに子連れ再婚を果たしたウルマンは、結婚式に父親のイングマール・ベルイマン(スウェーデンを代表する映画監督)が遂に姿をあらわさなかったエピソードが、日本の新聞でも取り上げられていましたね。 ニューヨーク大学で文学を勉強し、ダーグブラーデ紙の記者・コラムニストとして知られた彼女は、99年に小説デビューを果たします。「あなたが眠る前」(Før du sover)は、ノルウェーでは10万部の大ヒット(人口400万の国です!)を記録し、デビュー作ながら30ヶ国語に翻訳されます(No,23をご参照ください)。当然、次回作への期待は高まります。 最新作のタイトルは、「あなたのところにいる時」("Når jeg er hos deg" , Tiden社)です。アフテンポステン紙の書評(2001年10月8日)より、内容を紹介しましょう。 本の冒頭、女性が8階のアパートから、転落し、死亡します。彼女の死は、自殺なのか他殺なのか、また事故だったのかわからず、本の中でもはっきりした答えは出ません。その場にいた彼女の夫、娘、友人を通して、死んだ女性と夫との関係−暴力的で、問題の多かった愛情関係が浮かび上がってきます。 こちらの書評では、大絶賛!の様相で、「読まずに入られない小説!」と断言。これは注文しなくちゃな、と思わず焦るほどです。 同紙に掲載されたウルマンへのインタビュー(2001年10月5日)によると、女性が落ちたアパートは、実際にあるもので、ウルマンもそこまで上がったことがあるそうです。ただしウルマンは高所恐怖症。やっぱり、行った時はこわかったそうです。ごくろうさま。 「女性が高い場所から転落死して、その死んだ彼女について、真相を探ろうとする」。それだけ聞くと、ヒッチコックの「めまい」を連想しますが、出版社の宣伝文句によると、「愛の偽りについてのめまいを起こすような物語」だそうです。は〜。 2作とも、作家はともに30代。現代ノルウェーの断片を知る手がかりにもなるでしょう。また実際に、ノルウェー人が使っているノルウェー語に触れることができる意味でも、読む価値はあると思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 ・映画・音楽の 話 題 |
No23(9/10) 「最近の話題」欄同様、7月初旬から8月末までのノルウェー滞在中に集めた情報を、(少々、タイムラグはありますが)一挙に紹介致しましょう! ・フリーマーケットで自作の本を売る作家 毎週土曜日、オスロのフログネル・マヨースチューエン地区で催されているフリーマーケット「西地区の市場」(Vestkantstorget)は、たくさんの出店と人手で、にぎやかな雰囲気です。売られているのは、食器類やちょっとしたインテリア雑貨が多いのですが、その中に異色の出店がありました。 初老の男性と小さな女の子が店番をしているその出店には、1種類の物しか売られていません。それは、「クヌート・ハムスンと彼の十字架」(Knut Hamsun og hans kors)という本です。そして売っているのは、作家自身であるアーネ・トゥーミール(Arne Tumyr)氏。わずか49クローネ(約700円)で売られていますが、ハードカバーの立派な本です。 アーネさんにいろいろ話しかけてみました。私がオスロでノルウェー文学の講義を受講したことなどを話すと、「君にこの本をあげるよ」と、気前良く本を贈呈してくれ、サインにも応じてくれました。彼の隣にいた女の子は、彼のお孫さんだそうで、「彼女はとても優秀な売り子で、もう20冊も売ったんだよ」とのこと。Bra! 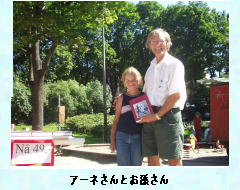 さて肝心の本ですが、これはノルウェーを代表する作家クヌート・ハムスンについてのドキュメント。彼はノーベル文学賞を受賞するなど名声が確立した作家ですが、同時に戦時中、対ナチス協力をした過去によって、今でもノルウェー人の中には、彼を認めない人がいます。アーネさんは、膨大な資料や貴重な写真などを紹介しながら、ハムスンの戦時中の行動・思想について分析を試みました(おそらく。というのも、本書は500ページに及ぶ大作で、とてもまだ読みきれません!ごめんなさい、アーネさん!)。 さて肝心の本ですが、これはノルウェーを代表する作家クヌート・ハムスンについてのドキュメント。彼はノーベル文学賞を受賞するなど名声が確立した作家ですが、同時に戦時中、対ナチス協力をした過去によって、今でもノルウェー人の中には、彼を認めない人がいます。アーネさんは、膨大な資料や貴重な写真などを紹介しながら、ハムスンの戦時中の行動・思想について分析を試みました(おそらく。というのも、本書は500ページに及ぶ大作で、とてもまだ読みきれません!ごめんなさい、アーネさん!)。この本の正価はたぶん5000円以上したと思いますが、思い切った値下げで自ら本を売っているアーネさんは、アフテンポステン紙にも取り上げられました。私も、拙著「私のノルウェー留学」をアーネさんの隣で売ろうかしら?とちょっと考えた1日でした。 蛇足:思いっきりロマンティックな恋愛もの、すれ違いものが好きな方!ハムスンの「Victoria」はお勧めです。ちゃんと「ヴィクトリア ある愛の物語」(猪苗代英徳訳、日本図書刊行会)という題で翻訳されてます。作品も翻訳もすばらしく、読書の秋にふさわしい1冊。 ・大学の先生兼ジャズボーカリストってかっこいい! オスロカレッジ(Høyskolen i Oslo)で、学校におけるジェンダー教育や教員養成を専門とするアンネ・リーセ・アーネセン(Anne-Lise Arnesen)助教授は、本職以外にジャズボーカリストの顔があります。彼女のお宅でテイクアウトの中華料理をご馳走になってから、新作のCD「Stemninger」(「雰囲気」という意味)を聴かせてもらいました。 とても落ち着いたリズムに彼女の渋い歌声が、合ってます。全5曲入りで、作詞作曲もアンネ・リーセさんが担当。「大人の雰囲気〜」と、聴きながらうっとり。テキストはノルウェー語ですので、ジャズファンのみならず、ノルウェー語を勉強中の人にもお勧めのCDです。 彼女の本職にも触れましょう。90年代、北欧5カ国を網羅した、学校におけるジェンダー教育や教員養成を調査・研究プロジェクトのコーディネーターを務めた彼女は、現在、同テーマで博士論文を執筆中。かなりの大作になるとか。完成が楽しみです。 それにしても、大学の先生をやりながら、ジャズもこなすなんてかっこよすぎ、ですよね?できる人は幾つもの才能があるんだな〜と、しみじみ。 ・好調なノルウェー映画と、お母さんがノルウェー人の有名女優 99年から1年間のオスロ留学時は、1回もノルウェー映画を観るために映画館に足を運ばなかったことに、今でも良心の痛み(え、あったの?の声あり)を覚えますが、今回の滞在中は、なかなかノルウェー映画が盛り上がっていたので、「最低ノルウェー映画1本をみる」ノルマを果たすことができました。パチパチ! ドイツのハンブルグに住んでいるノルウェーの人気作家、イングヴァール・アンビョルセン(Ingvar Ambjørsen)の小説「Brødre i blodet」(「血を分けた兄弟」の意味でしょうかね?)をベースに映画化した「Elling」(「エッリン」)は、商業的にも批評家受けも良く、評判だったので、オスロのサーガ映画館(Saga)まで観に行って参りました〜。 「Elling」の主人公、エッリンが、母親の死後、精神医療施設に収容され、同じ施設で暮らしていたヒェル・ビャルネ(Kjell Bjarne)と、オスロ市が管理するマヨースチューエンのアパートで暮らし始めるところから物語は始まります。 電話をかけること、店に入って買い物すること、町を歩くこと、といった普段、誰もがこなしていることがエッリンにとって苦痛そのもの。 徐々に、彼とヒェル・ビャルネが「普通の」生活を送れるようになる過程を、アパートの上に住む妊婦ライドゥン(Reidun)と、大学で文学を教えていたアルフォンス(Alfons)もまじえて、コミカルに、時にブラックユーモア的に綴っていきます。とりわけ、エッリンのモノローグ(彼の正し過ぎる内面が吐露)が笑いを誘います。また、彼が部屋に張っている中年女性のポスターは、かのグロー・ハーレム・ブルントラン元首相(現在はWHO事務総長)という渋い趣味! 以前、紹介した「ジャンクメール」同様、「きれいな人が全く出てこない」映画とも言えます。登場人物は、みなくたびれた中年男性・女性で(でもリアルティー満点!)、華やかさとは皆無。ヒェル・ビャルネは、原作では150キロの巨体という設定なので、演じたSven Nordin(スヴェイン・ノーディン)は、この役作りのためにわざわざ太ったそうです(よ!ノルウェーのロバート・デニーロ!)。彼の役は、「全く下着を換えない」人物という設定もありましたが、ちゃんとそれも守ったように見えるほど、画面から「におってきそうな」雰囲気でした。 監督のPetter Næss(ペッテル・ナッス)は、Erlend Loeのデビュー小説「Tatt av kvinnen」(「風と共に去りぬ」をもじったタイトルなので、さしずめ「女と共に去りぬ」?)の舞台化にも挑戦するそうで、こちらも観てみたいな〜と思います。 少し原作にも触れましょう。主人公Ellingを描いた小説はシリーズ化しています。 「Utsikt til paradiset」(「天国の眺め」1993)、「Fugledansen」(「鳥のダンス」1995)、「Brødre i blodet」(「血を分けた兄弟」1996)、「Elsk meg i morgen」(「明日、愛して」1999)と続いています。映画を観た後、原作を読みましたが、映画でも登場したエッリンのモノローグがさらに楽しめます。 いずれにしても、幾つかの国で上映が決まった本作品は、日本でも、もしかしたら上映の機会があるかもしれませんね。 宣伝:作者イングヴァール・アンビョルセンのホームページ(http://www.kjentfolk.no/forfattere/ambjornsen) 残念ながらノルウェー語だけのサイトですが、なかなか味のある作者のお顔が楽しめます。ちなみに私の知人にそっくり(日本人男性ですけど)。 映画の話題をもう1つ。 ノルウェー映画ではないのですが、日本より一足お先に「ブリジッド・ジョーンズの日記」を観てきました。ノルウェーでの興行成績は絶好調で、あの「パール・ハーバー」よりもお客さんは入っていたでしょう。 主役のブリジットを演ずるレニー・ゼルウィガーは、お父さんがスイス人、お母さんがノルウェー人だそうで、ノルウェーのマスコミではしきりに、「彼女のお母さんはノルウェー人=だから彼女は、ほとんどノルウェー人なんだよ」的に盛り上がってました。残念ながら、日本の映画ジャーナリストたちは、あまりそこまで着目していないようですね。Ummm... ・ノルウェーの翻訳事情 私も何度か翻訳の仕事をしたので、ノルウェーの翻訳家たちにも興味あります。日本以上に、ノルウェーでは陽のあたらない翻訳家たちについて、8月9日付ダーグブラーデ紙は、モルデで行われた「ビョルンソン・フェスティバル」に関連してレポートしています。 まず統計から。「ノルウェー翻訳家協会」には280人のメンバーがいますが、フルタイムで翻訳をしているのは、わずか25人。そして平均年収は、約250万円(キビシー!)で、1ページあたりの翻訳料は約2500円だそうです。今、もっとも有名な翻訳家は、Kjell og Kari Risvik(ヒェッルとカーリ・リースヴィーク夫妻)で、何ヶ国語かをこなされると聞きました。 同じ紙面では、作家の側から「翻訳の大切さ」を訴えています。お父さんは映画監督のベルイマン、お母さんは女優・映画監督のリブ・ウルマンという「セレブ夫婦」の娘であり、作家のリン・ウルマン(Linn Ullmann)は、デビュー小説が30ヶ国語に翻訳されたそうですが、次のように語っています。 「私の本が英語に試訳された原稿を読んで、ほとんど泣きそうになった。例えば、「クリスマスのお祝い」(Julefeiring)が、「7月のお祝い」(feiring i juli)となっていました。だから、私が新しい翻訳家を見つけなくてはならなかったのです」。さらに、リン・ウルマンは、ノルウェーの翻訳家たちが、あまり大事にされていないとも指摘しています。 翻訳が悪いと、その国で売上と批評に悪影響が及ぶ例として、前出のクヌート・ハムスンの名前が挙げらています。彼の作品が、イギリスで成功したかったのは、初期の翻訳が良くなかったとか。また、スペイン語の翻訳でも、誤訳があるそうです。 リン・ウルマンは、自作の翻訳の出来には非常に心を砕いているそうで、その国の知り合いや友人を通して、翻訳が間違っていないかチェックしているそうです。もし、日本語に翻訳されたら、彼女はやはり、日本語のできる人にチェックしてもらうのでしょうか?試したい方は、彼女のデビュー作「Før du sover」(「あなたが眠る前」)の翻訳にトライしてみてはいかが? ・人気作家の児童文学 ノルウェーでは、大人向けの作品・子供向けの作品を書く作家が多いことは、私の「ノルウェーの児童文学と女性文学」という講演の中で言及しましたが、若手人気作家No.1のErlend Loe(アーレン・ロー)もその一人。 「最近の話題」欄で、彼が左派社会党(SV)の選挙キャンペーンで、自作の詩を朗読して、周りをさむ〜い空気にしてしまったエピソードを紹介しましたが、その元ネタである「Kurt」シリーズの本を紹介しましょう。 今年発売された「KURT³」(Cappelen社)は、主人公Kurtを描いた作品ですでに発表済みの3作をまとめたもの。 彼の文体は、大人向け小説でも子供向け小説でも、短く簡潔な文章が続きます。普通の児童文学の枠を超えた想像力と現代社会に対するアイロニー、そして「していいこと・いけないこと」の明確な線引きが心地よい作品群です。 さらに特筆すべきは、イラストのすばらしさ!Kim Hiorthøyの描くイラストは、ほぼ全ページを埋めていますが、ユーモラスでとぼけた作風は、テキストに合ってます。 簡単な単語、短い文章、たくさんの絵。そして、おもしろい内容。ぜひ、ノルウェー語学習中の方、お手にとってください!ノルウェー語読めない方は、絵だけでも楽しめます! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 の 話 題 |
No22(7/8) ノルウェーの現代文学を代表する作家のひとり、Dag Solstad(ダーグ・ソルスター)が、7月9日でとうとう60歳になるそうです。Gratulerer med dagen!(お誕生日おめでとう!) 7月5日付のアフテンポステン紙によると、今度、彼のインタビューをまとめた本が出版されることが報道されています。インタビュアーは、ベルゲンの新聞「Bergens Tidende」紙の記者、Jan H. Landro氏。Landro氏は、19年間にわたってソルスター相手に12回のインタビューを試みたそうです。これらのインタビューは、すでに「Bergens Tidende」紙に掲載されているものもありますが、ほとんどが未発表のもの。 ソルスター自身は、自分が80年代に受けたインタビューについて「今とは考え方が違って驚いている」とコメントしています。 私自身、彼の作品は大好きですが、インタビュー集というとまた違った期待があります。 というのも、ソルスターは「書くものは明晰だが、話している彼は理解不能」作家として有名。テレビのインタビュー番組を見たことがありましたが、視線は頼りなく空を泳ぎ、言ってることは...「字幕つけて!」と叫びたくなりました。 そんな彼を相手に、1982年からインタビューを続けた記者は、すごい忍耐力の持ち主ではないか?と興味はつきません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彫 刻 の 話 題 |
No21(6/22) この話題をここに載せるのが、正しいのか悩みつつ...。アフテンポステン紙6月21日付の記事より。 ノルウェー第3の都市、トロンハイムには「ニーダロス大聖堂」という有名な教会があります。この壮麗な大聖堂は、中世期に建設された大聖堂としては、北欧随一と言われ、ノルウェーを代表する建造物です。 このニーダロス大聖堂は、1869年に修復工事が行われ、100年後の1969年には、北西にある塔に聖ミカエルの天使像が新たに置かれました。以来、「天使像が、アメリカの有名なシンガー、ボブ・ディランに似ている」という噂が、広まってしまいました。しかし、天使像の生みの親である彫刻家のクリストファー・ライルダールが、この噂について認めなかったため、噂の域を超えることはなかったのです。 しかし、今年85歳になるライルダールが、あと数日後にボブ・ディランがトロンハイムにやって来るこの時期になって、噂の真相を語りました。 「ああ、本当じゃよ(注:年齢にあわせて翻訳)。わしが、聖ミカエル像を作ったとき、ボブ・ディランの顔をモデルに使ったんじゃ。彼がベトナム戦争に抗議する代表者となった時、彼の顔を見たんじゃ」。ラインダールは、ディランの歌も好きだそうで、「わしは、塔のてっぺんと、偉大な詩人がマッチすると思ったんじゃ」とも語っています。 重大な告白をした彫刻家氏は、この天使像が注目を集めないで欲しいと願っています。 「教会の人たちが、どう思うかわからんし、ボブ・ディラン自身が、それを聞いたら何て言うじゃろう」。 渦中の人、ボブ・ディランは、6月24日にトロンハイムにやって来ます(彼の顔を知らない方、こちらからどうぞ)。 「マイブーム」の火付け役、漫画家・コラムニストのみうらじゅん氏は、自身の「マイブーム」の中に、ボブ・ディラン熱が含まれていることは、周知の事実(?)ですが、ぜひトロンハイムにまで行って、実物を確かめて欲しいですね。みうら氏は、仏像好きでもあるから、天使像も興味あるでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
