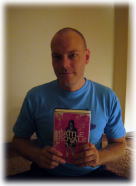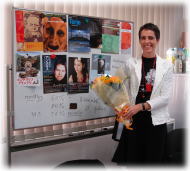夢ネット特選インタビュー

|
「日本ではノルウェーはマイナーで・・・・」
そんな言葉を良く耳にしますし、実際に口にもするのですが、それでも仕事や趣味、学習などの分野でノルウェー通として活躍されている方々がたくさんいらっしゃいます。
ここではノルウェーに携わる多方面の方々の生の声を、インタビュー形式でご紹介していきたいと思います♪
|
 |
 |
ピアノ・チェンバロ奏者 長崎美穂子さん(07.01.20)
プロフィール
 長崎美穂子(ながさき・みほこ)さん: 元ベルゲン交響楽団ピアニスト 長崎美穂子(ながさき・みほこ)さん: 元ベルゲン交響楽団ピアニスト
日本・ノルウェー音楽家協会会員
長崎さんのHP:「海の見える音楽室」
7年間にも渡るノルウェーでの留学と演奏家経験をお持ちの長崎美穂子さん。
2007年はノルウェーを代表する作曲家グリーグの没後100年という節目にあり、たくさんのイベントやコンサートが催されます。その中でも中心的に活躍されている長崎さんに、主にベルゲンでの留学生活についてお話をうかがいました。
|

 今日はサロンで楽しいお話をありがとうございました。 今日はサロンで楽しいお話をありがとうございました。
演奏なしで、講演だけといったご経験は今回が初めてですか?
 はい。講演だけは初めてですね。 はい。講演だけは初めてですね。
 92年にベルゲン音楽院(現:グリーグアカデミー)に留学をされたそうですが、留学前に日本でノルウェー語の勉強はなさいましたか? 92年にベルゲン音楽院(現:グリーグアカデミー)に留学をされたそうですが、留学前に日本でノルウェー語の勉強はなさいましたか?
 当時は東京にいたのですが、ノルウェー大使館に問い合わせをし、ノルウェー語を勉強できるところを探しました。語学学校はあっても、初心者コースが開講されておらず、結局、スウェーデン語の文法が分かる日本人の方にプライベートでレッスンを受けました。 当時は東京にいたのですが、ノルウェー大使館に問い合わせをし、ノルウェー語を勉強できるところを探しました。語学学校はあっても、初心者コースが開講されておらず、結局、スウェーデン語の文法が分かる日本人の方にプライベートでレッスンを受けました。
 そもそも、ノルウェーへ留学を決めた理由は何でしょう? そもそも、ノルウェーへ留学を決めた理由は何でしょう?
 ヨーロッパへの留学を希望していました。最初はドイツを考えていましたが、グリーグの音楽に惹かれ、それからは関心がノルウェーへ移りました。そんな折、友達が、雑誌“ショパン”に“ベルゲン音楽院”の広告が載っているよ、と教えてくれたのです。91年の秋ですね。自分の経歴とあなたの学校で勉強をしたい、と書いた手紙を学校へ送りました。すると、とても丁寧なお返事をいただき、ぜひ3月の試験を受けに来なさい、と勧められました。 ヨーロッパへの留学を希望していました。最初はドイツを考えていましたが、グリーグの音楽に惹かれ、それからは関心がノルウェーへ移りました。そんな折、友達が、雑誌“ショパン”に“ベルゲン音楽院”の広告が載っているよ、と教えてくれたのです。91年の秋ですね。自分の経歴とあなたの学校で勉強をしたい、と書いた手紙を学校へ送りました。すると、とても丁寧なお返事をいただき、ぜひ3月の試験を受けに来なさい、と勧められました。
 ちゃんと返事が来ただけですごいですね。 ちゃんと返事が来ただけですごいですね。
 当時、ベルゲン音楽院にはちゃんとした留学生の受け入れ制度が整っていませんでしたが、国際化を目指していたようです。学校側の意志とうまく合致したのでしょうね。 当時、ベルゲン音楽院にはちゃんとした留学生の受け入れ制度が整っていませんでしたが、国際化を目指していたようです。学校側の意志とうまく合致したのでしょうね。
 試験について教えて下さい。 試験について教えて下さい。
 高校で教える仕事をしていたので、いきなり3月にノルウェーへ受験に来なさいと言われても無理でした。すると、テープ審査で良し、となりテープを送り合格となりました。 高校で教える仕事をしていたので、いきなり3月にノルウェーへ受験に来なさいと言われても無理でした。すると、テープ審査で良し、となりテープを送り合格となりました。
 スムーズに事が運んだのですね。 スムーズに事が運んだのですね。
 テープ審査だけでは不十分なので、現地に到着後、実際に歌ってみるように言われました。とても和やかな雰囲気で、先生が“スキヤキソング”を弾いて歓迎してくれました。私はグリーグの“春”をノルウェー語で歌ったのですが、それ1曲でOK!!となりました。グリーグの勉強をしたい、と言うとノルウェー人はとても喜んでくれましたね。 テープ審査だけでは不十分なので、現地に到着後、実際に歌ってみるように言われました。とても和やかな雰囲気で、先生が“スキヤキソング”を弾いて歓迎してくれました。私はグリーグの“春”をノルウェー語で歌ったのですが、それ1曲でOK!!となりました。グリーグの勉強をしたい、と言うとノルウェー人はとても喜んでくれましたね。
 ベルゲンでは学生寮にお住まいになったのですか? ベルゲンでは学生寮にお住まいになったのですか?
 音楽院には学生寮はありませんでした。でも住所が決まらないと荷物が送れないので、困っていたところ、学生寮に部屋を確保してもらえました。92年秋から入寮しましたが、日本人は私だけで珍しがられましたね。 音楽院には学生寮はありませんでした。でも住所が決まらないと荷物が送れないので、困っていたところ、学生寮に部屋を確保してもらえました。92年秋から入寮しましたが、日本人は私だけで珍しがられましたね。
 留学後、言葉の問題はありましたか? 留学後、言葉の問題はありましたか?
 どうでしょうね・・・。1年目は無我夢中で過ぎていきました。最初の3ヶ月、移民向けの無料ノルウェー語コースに通い、ベルゲン大学でも勉強しました。ベルゲンの方言、とくにrの音の聞き取りが難しかったですね。 どうでしょうね・・・。1年目は無我夢中で過ぎていきました。最初の3ヶ月、移民向けの無料ノルウェー語コースに通い、ベルゲン大学でも勉強しました。ベルゲンの方言、とくにrの音の聞き取りが難しかったですね。
 長崎さんのノルウェー語は、ベルゲン風? 長崎さんのノルウェー語は、ベルゲン風?
 自分ではいろいろ混ざっていると思うのですが、日本でノルウェー大使とお話した時に、“あなたはベルゲンにいましたね”とばれました。 自分ではいろいろ混ざっていると思うのですが、日本でノルウェー大使とお話した時に、“あなたはベルゲンにいましたね”とばれました。
 長崎さんは、音楽院での勉強以外に、ベルゲンで演奏活動をされましたね。 長崎さんは、音楽院での勉強以外に、ベルゲンで演奏活動をされましたね。
 はい。ベルゲン交響楽団での演奏や、合唱団のピアノ伴奏、オーディションでの伴奏などいろいろな経験をしました。フレキシブルに対応できることが大事だったと思いますね。こんなこともありました。朝の9時、まだ寝ていた時に電話がかかってきて、11時のスクールコンサートで演奏してくれ、といきなり頼まれて、急いで支度をして、演奏したんですよ。 はい。ベルゲン交響楽団での演奏や、合唱団のピアノ伴奏、オーディションでの伴奏などいろいろな経験をしました。フレキシブルに対応できることが大事だったと思いますね。こんなこともありました。朝の9時、まだ寝ていた時に電話がかかってきて、11時のスクールコンサートで演奏してくれ、といきなり頼まれて、急いで支度をして、演奏したんですよ。
 お話をうかがっていると、長崎さんのノルウェーの生活はとても楽しそうですよね。ノルウェー人度チェックでは98点(過去最高得点)でしたし、ノルウェーとは相性が良かったのでしょうか? お話をうかがっていると、長崎さんのノルウェーの生活はとても楽しそうですよね。ノルウェー人度チェックでは98点(過去最高得点)でしたし、ノルウェーとは相性が良かったのでしょうか?
 はい、とても楽しかったですね。ノルウェーの田舎生活も平気でしたし、なによりも“楽”に感じました。でもニューヨークにいた方は、ノルウェー暮らしが辛そうでしたね。 はい、とても楽しかったですね。ノルウェーの田舎生活も平気でしたし、なによりも“楽”に感じました。でもニューヨークにいた方は、ノルウェー暮らしが辛そうでしたね。
 ノルウェーの食生活はいかがでしたか? ノルウェーの食生活はいかがでしたか?
 問題なかったですね。夫はダメでしたが・・・。 問題なかったですね。夫はダメでしたが・・・。
 長崎さんは、ベルゲンで知り合った日本人の方とご結婚されたとか? 長崎さんは、ベルゲンで知り合った日本人の方とご結婚されたとか?
 はい。夫は95年から1年間、ベルゲン大学に研究留学して、知り合いました。後に私が結婚した、と聞いて周りの反応は“当然、ノルウェー人と結婚したんでしょう?”でしたね。ずっとベルゲンにいて、岡山出身の日本人と結婚??って驚かれました。 はい。夫は95年から1年間、ベルゲン大学に研究留学して、知り合いました。後に私が結婚した、と聞いて周りの反応は“当然、ノルウェー人と結婚したんでしょう?”でしたね。ずっとベルゲンにいて、岡山出身の日本人と結婚??って驚かれました。
 素晴らしい出会いがあったのですね。羨ましい限りです・・・。さて、たくさんのエピソードがあると思いますが、「これはノルウェー人っぽいな~」というものがあれば教えて下さい。 素晴らしい出会いがあったのですね。羨ましい限りです・・・。さて、たくさんのエピソードがあると思いますが、「これはノルウェー人っぽいな~」というものがあれば教えて下さい。
 まず、ノルウェー人はあまり計画性がないですね。声楽科時代に、クラスメートと民族衣装のブーナッドを着て、夏の観光客向けに催されるコンサートで歌うバイトをしました。でも、どうもお客の入りが良くない・・・。そこでクラスメートは、“そうだ、観光客が泊まっているホテルに行って、朝食のテーブルでPR用に歌ってみよう”と言い出したんです。私は、“日本人の観光客は大体、ベルゲンに1泊しかいないから、朝はホテルにいてもコンサートが開かれる夜には、もういないよ”と反対したんです。でもみんなは、“いい思い付きだ!”って盛り上がって、朝の7時にブーナッドを着る羽目に・・・。ホテルで歌うと確かに喜ばれて、写真もたくさん撮られました。ただ私の予想通り、みんな夜にはベルゲンを発ってしまうのですね。コンサートにお客さんは増えなかったです。3日目に効果のなさをようやく悟って、止めました。最初から分かりそうな話なのに・・・。 まず、ノルウェー人はあまり計画性がないですね。声楽科時代に、クラスメートと民族衣装のブーナッドを着て、夏の観光客向けに催されるコンサートで歌うバイトをしました。でも、どうもお客の入りが良くない・・・。そこでクラスメートは、“そうだ、観光客が泊まっているホテルに行って、朝食のテーブルでPR用に歌ってみよう”と言い出したんです。私は、“日本人の観光客は大体、ベルゲンに1泊しかいないから、朝はホテルにいてもコンサートが開かれる夜には、もういないよ”と反対したんです。でもみんなは、“いい思い付きだ!”って盛り上がって、朝の7時にブーナッドを着る羽目に・・・。ホテルで歌うと確かに喜ばれて、写真もたくさん撮られました。ただ私の予想通り、みんな夜にはベルゲンを発ってしまうのですね。コンサートにお客さんは増えなかったです。3日目に効果のなさをようやく悟って、止めました。最初から分かりそうな話なのに・・・。
 ありがちなお話ですね~。それにしても、長崎さんの留学や演奏家としての生活は全て、“先駆的”という言葉があてはまると思いますが。 ありがちなお話ですね~。それにしても、長崎さんの留学や演奏家としての生活は全て、“先駆的”という言葉があてはまると思いますが。
 そうですね。当時はインターネットで情報収集とかできない時代だったので、いろいろ大変でした。今は各大学がHPを持っているので、情報収集は楽ですよね。グリーグアカデミーは、私が初めての日本人留学生でしたが、今では毎年、日本人学生が2,3人留学しています(交換留学制度がスタート)。私が留学した頃と今では、大学のシステムや留学生受け入れ態勢も変化しているようです。 そうですね。当時はインターネットで情報収集とかできない時代だったので、いろいろ大変でした。今は各大学がHPを持っているので、情報収集は楽ですよね。グリーグアカデミーは、私が初めての日本人留学生でしたが、今では毎年、日本人学生が2,3人留学しています(交換留学制度がスタート)。私が留学した頃と今では、大学のシステムや留学生受け入れ態勢も変化しているようです。
 最後にノルウェー音楽の魅力について教えて下さい。 最後にノルウェー音楽の魅力について教えて下さい。
 先日放送された“N響アワー”(北欧音楽特集)で池辺晋一郎さんが“寒い国の音楽”と形容されていましたね。確かに、雪や氷など寒い気候の静謐感がイメージされますが、音楽の内面には、暖かさを感じます。音楽を聴いていると、自然の風景が思い浮かんできます。ノルウェーの音楽は、四角四面のコンサートホールより、木のぬくもりがある木造教会や建物で演奏される方が合っていますね。 先日放送された“N響アワー”(北欧音楽特集)で池辺晋一郎さんが“寒い国の音楽”と形容されていましたね。確かに、雪や氷など寒い気候の静謐感がイメージされますが、音楽の内面には、暖かさを感じます。音楽を聴いていると、自然の風景が思い浮かんできます。ノルウェーの音楽は、四角四面のコンサートホールより、木のぬくもりがある木造教会や建物で演奏される方が合っていますね。
 本日は、どうもありがとうございました。 本日は、どうもありがとうございました。
■サロンとインタビューを終えて
今日は風邪を引いていて、声があまり・・・」と恐縮していた長崎さん。それでも、十分、透明感のある美しい声が印象的でした。長崎さん自身が、ノルウェーの自然そのもののようです。留学への経緯やその後のベルゲンでの生活など、とても楽しかったご様子がうかがえました。「相思相愛」という言葉は、男女間だけではなく、長崎さんとノルウェー(ベルゲン)の間にも当てはまるのではないでしょうか?
「グリーグ2007」、楽しみです。
「ノルウェーについて学ぶサロン」レポート(第10回)
■参考URL
グリーグ2007:http://www.grieg2007.com/
日本・ノルウェー音楽家協会:http://jnms.web.infoseek.co.jp/
←特選インタビューへ戻る
|
 |
 |
国際木質文化研究所 雨宮 陸男さん (06.11.30)
プロフィール
 雨宮 陸男(あめみや・むつお)さん: 国際木質文化研究所 代表取締役 雨宮 陸男(あめみや・むつお)さん: 国際木質文化研究所 代表取締役
北欧建築・デザイン協会(SADI)理事・ノルウェー担当
大規模木造建築の研究分野がご専門の雨宮さんは、ヨーロッパを中心に国際的な活動をされている建築のスペシャリストです。20年ほど前からノルウェーに関わり、現在は北欧建築・デザイン協会(SADI)の理事も務められ、ノルウェーをご担当されています。
この度、そんなノルウェーつながりで、ノルウェー夢ネットのインタビューに快く応じてくださいました。
以前から「ノルウェー建築」に興味津々のYoko@管理人 より、レポートさせていただきます。frosk編集人 より、レポートさせていただきます。frosk編集人 も同席していました。 も同席していました。
|

 雨宮さんとノルウェーとの関わりについて教えてください。 雨宮さんとノルウェーとの関わりについて教えてください。
 ノルウェーには1986年から行っています。大規模木造建築を専門にしていたことからNTI(Norsk Treteknisk Institutt・ノルウェー木材工学研究所)とコンタクトをとり、研究者が集まって交流が生まれました。それからは2年に1度のペースでノルウェーを訪れています。これまでノルウェーのフローリングや壁のメーカーを日本に紹介することもして参りましたが、日本市場に入ったのは北欧の中でもノルウェーが一番早かったんですよ。 ノルウェーには1986年から行っています。大規模木造建築を専門にしていたことからNTI(Norsk Treteknisk Institutt・ノルウェー木材工学研究所)とコンタクトをとり、研究者が集まって交流が生まれました。それからは2年に1度のペースでノルウェーを訪れています。これまでノルウェーのフローリングや壁のメーカーを日本に紹介することもして参りましたが、日本市場に入ったのは北欧の中でもノルウェーが一番早かったんですよ。
 そうなんですか?日本でよく目にする建材はフィンランドやスウェーデン製のイメージがあるのですが。 そうなんですか?日本でよく目にする建材はフィンランドやスウェーデン製のイメージがあるのですが。
 ご存知のように、ノルウェー人は気質的に他国と競合するとあっさりひいてしまうことが多いようです。そうまでして日本に売らなくていいと(笑)。でも、レッドパインの床材メーカーなどで残っているところもありますよ。 ご存知のように、ノルウェー人は気質的に他国と競合するとあっさりひいてしまうことが多いようです。そうまでして日本に売らなくていいと(笑)。でも、レッドパインの床材メーカーなどで残っているところもありますよ。
長野オリンピックの時、ノルウェービレッジではノルウェーのHEBE(ヘーベ)社が考案したシステム住宅が採用になりました。小さな別荘のような建物ですが、経済的で快適な素晴らしい住宅です。日本でも、阿蘇や那須高原、軽井沢などに建てられています。
 白馬村のノルウェービレッジには私も行ったことがあります!オリンピックが終わってからのことですが。 白馬村のノルウェービレッジには私も行ったことがあります!オリンピックが終わってからのことですが。
ところでノルウェーの大規模木造建築と伺ったとき、オスロ新空港Gardermoen空港の集成材でできた巨大な梁を思い浮かべました。無機質になりがちな大空間に木のぬくもりが感じられて、私は個人的にも大好きなところです。
 あの建物は私も工事中から完成まで3回の視察に行きました。レポートもありますので、ご興味があればどうぞご覧下さい。他にリレハンメル・オリンピック施設について私が報告した建築誌(日経アーキテクチュア)や、ノルウェーの木の文化を特集した雑誌(輸入住宅を呼べる家)も参考にお持ちしました。 あの建物は私も工事中から完成まで3回の視察に行きました。レポートもありますので、ご興味があればどうぞご覧下さい。他にリレハンメル・オリンピック施設について私が報告した建築誌(日経アーキテクチュア)や、ノルウェーの木の文化を特集した雑誌(輸入住宅を呼べる家)も参考にお持ちしました。
 それは貴重な資料をありがとうございます。日本でノルウェーの建築について書かれたものは本当に少ないですよね。これまで、こんな詳しい特集が組まれていたなんて知りませんでした。雨宮さんはノルウェーのどんなところに惹かれているのでしょうか? それは貴重な資料をありがとうございます。日本でノルウェーの建築について書かれたものは本当に少ないですよね。これまで、こんな詳しい特集が組まれていたなんて知りませんでした。雨宮さんはノルウェーのどんなところに惹かれているのでしょうか?
 そうですね。ノルウェー人ののんびりさ、あくせくしないところ、商売にこだわらないところが大好きです。仕事柄、スウェーデン人やフィンランド人とも接しましたが、ノルウェー人がいちばん付き合いやすいですね。彼らは私がノルウェーを訪ねるときはいつも家族のように暖かく迎えてくれます。家でご馳走を振る舞ってくれたり、別荘(Hytta)に招待してくれたり。ご馳走と言っても茹でた海老とサラダ、ワインだけだったりもしますが、とても美味しかったです。 そうですね。ノルウェー人ののんびりさ、あくせくしないところ、商売にこだわらないところが大好きです。仕事柄、スウェーデン人やフィンランド人とも接しましたが、ノルウェー人がいちばん付き合いやすいですね。彼らは私がノルウェーを訪ねるときはいつも家族のように暖かく迎えてくれます。家でご馳走を振る舞ってくれたり、別荘(Hytta)に招待してくれたり。ご馳走と言っても茹でた海老とサラダ、ワインだけだったりもしますが、とても美味しかったです。
  とってもよくわかりますね~。 とってもよくわかりますね~。
 私もノルウェーに遊びに行ったときに初日だけ知人が留守だったことがあったのですが、「家の鍵を隣のおばさん(もちろん私は面識のない方)に預けておくから受け取って泊まっててね。」と言われたときには驚きました。家も車も好きに使っていいと言うわけです。それがノルウェー流のおもてなしの心なんですよね。 私もノルウェーに遊びに行ったときに初日だけ知人が留守だったことがあったのですが、「家の鍵を隣のおばさん(もちろん私は面識のない方)に預けておくから受け取って泊まっててね。」と言われたときには驚きました。家も車も好きに使っていいと言うわけです。それがノルウェー流のおもてなしの心なんですよね。
ところで、雨宮さんにとってノルウェーの建築とはどんなものですか?またそれを日本でどのようにPRなさりたいのか教えてください。
 民族性、社会性、つまりその歴史やどんな生活をしているのかを学ぶことです。 民族性、社会性、つまりその歴史やどんな生活をしているのかを学ぶことです。
私はこれまでの研究を通して、ノルウェーの建築が生まれる背景を知りたいと思っています。例えばリレハンメル・オリンピックの施設は環境に配慮された素晴らしい計画が実現しました。オリンピックは自然環境を損なうものであってはならないという考え方を中心に、施設の規模を決め、動植物を保護し、建物を移転可能にするなど開催後々のことまで細かく決められていました。これらのことは、いきなりできることではありません。建築のエンジニアリングは世界共通ですが、私がノルウェーとの関わりの中で得た大切なものは「心」の部分です。
ノルウェーでは建築の「心」を学ぶ環境が幼少時代から整っているのではないかと考えています。日本では住宅を購入するときに初めて住まいについて考えるため、専門家との意思疎通ができずに建ててから後悔する例も多いと思います。ノルウェーではこどもの頃から住まいの材料や構造についての知識が身についているのではないでしょうか。今後、日本の幼児教育、児童教育の中で建築をどう教えていくのか、ノルウェーを参考に研究していきたいと考えています。
 ノルウェーの教育のカリキュラムに建築が含まれているかどうかはともかくとして、確かにノルウェー人たちは自分たちの手で壁を塗ったりして、家に手を加えていますよね。 ノルウェーの教育のカリキュラムに建築が含まれているかどうかはともかくとして、確かにノルウェー人たちは自分たちの手で壁を塗ったりして、家に手を加えていますよね。
 本格的に、増築している人なども見かけますよね。小さい頃からナイフを持たせて木を削らせたり、ブルドーザーのミニカーで遊ばせたり、特に家庭教育の中で自然と身につく何かがありそうです。 本格的に、増築している人なども見かけますよね。小さい頃からナイフを持たせて木を削らせたり、ブルドーザーのミニカーで遊ばせたり、特に家庭教育の中で自然と身につく何かがありそうです。
 そうなのです。ノルウェーでは本当に建物が大事にされていることを日本人にも伝えたいですね。自分で手を加えて愛情を注ぐことで思い出も重なっていくことでしょう。私は以前、ノルウェーで日本の木造建築について講演をしたことがあるのですが、彼らは大変真剣に聞いてくれました。1000年以上も守られ続けている日本の木造建築との間に、その精神性においてつながりがあるのだと思います。 そうなのです。ノルウェーでは本当に建物が大事にされていることを日本人にも伝えたいですね。自分で手を加えて愛情を注ぐことで思い出も重なっていくことでしょう。私は以前、ノルウェーで日本の木造建築について講演をしたことがあるのですが、彼らは大変真剣に聞いてくれました。1000年以上も守られ続けている日本の木造建築との間に、その精神性においてつながりがあるのだと思います。
 雨宮さんは北欧建築・デザイン協会(SADI)の理事でノルウェーをご担当されていらっしゃるとのことですが、その活動についてもお話を伺えますか? 雨宮さんは北欧建築・デザイン協会(SADI)の理事でノルウェーをご担当されていらっしゃるとのことですが、その活動についてもお話を伺えますか?
 はい。SADIには北欧好きの会員が集まり、定期的に講演会や研究会を催しています。ただノルウェーは情報が少なくて困っています。情報量としては、フインランド、スウェーデンが多いですから肩身が狭いですね(笑)。今後は、若い世代に興味をもってもらえるような活動を考えていきたいと思っています。 はい。SADIには北欧好きの会員が集まり、定期的に講演会や研究会を催しています。ただノルウェーは情報が少なくて困っています。情報量としては、フインランド、スウェーデンが多いですから肩身が狭いですね(笑)。今後は、若い世代に興味をもってもらえるような活動を考えていきたいと思っています。
本日は、久しぶりにノルウェーの仲間とお話ができて、とても楽しかったです。
  こちらこそ、楽しいお話をありがとうございました。 こちらこそ、楽しいお話をありがとうございました。
■インタビューを終えて
雨宮さんとは今回初めてお会いしたので、実は私たちの方が緊張していました。でも、待ち合わせ場所で一目見るなりその温厚なお人柄が感じられるお姿にすっかり安心し、あとはノルウェー仲間同士、ついつい長話をしてしまいました。
お忙しい中、私たちの素人インタビューにおつきあいくださったこと、この場を借りて改めて御礼申し上げます。
←特選インタビューへ戻る
|
 |
 |
ミニインタビュー with ノルウェーデザイナー (06.11.08)
プロフィール
 Jonas Ravlo Stokke(ヨナス・ラヴロ・ストッケ)さんとØystein Austad(オイステイン・オースタッド)さん Jonas Ravlo Stokke(ヨナス・ラヴロ・ストッケ)さんとØystein Austad(オイステイン・オースタッド)さん
: StokkeAustad(ストッケ・オースタッド) http://www.stokkeaustad.com/
二人組デザインユニット。2004年に結成されたばかりだが2005年にはノルウェー国内のデザイナートップ10
にもランク入りし、非常に注目度が高い。同年の新人賞も受賞している。
Øysteinはnorwaysaysの下でインターンとして活躍していた経験も。
 Svein H. Lia(スヴァイン・H.リーア)さんとDag Solhaug(ダーグ・ソールハウグ)さん Svein H. Lia(スヴァイン・H.リーア)さんとDag Solhaug(ダーグ・ソールハウグ)さん
: Bleed designstudio(ブリード・デザインスタジオ) http://www.bleed.no/
オスロを中心として活躍するグラフィックデザインチーム。2006年6月から活動を開始し多数の賞を受賞。
現在は14名のメンバーがおりノルウェー国内で最も有名なグラフィックチームといっても過言ではない。
国内外を問わず幅広く活動、norwaysaysをはじめとするプロダクトデザイターとのコラボレーションでも
非常に高い評価を受けている。
 Charlotte Karlsen(シャルロット・カールセン)さん Charlotte Karlsen(シャルロット・カールセン)さん
: SynchronizedLiquid(シンクロナイズドリキッド) http://www.synchronizedliquid.com/
ノルウェー出身、イギリス在住のガラス作家。1999年にスウェーデンのコスタボダグラススクールを卒業後、
世界中のあらゆる展示会にて作品を発表してきた。2002年よりシンクロナイズドリキッドとして活動開始。
いずれの作品も色彩が美しく、女性らしくやわらかいデザインが特徴。
注)ノルウェー語カタカナ表記は、「Design Tide」の公式パンフレットに掲載のあるものはそれに準じました。
「木更津キャッツアイ」のぶっさんも興味がある「北欧インテリア」。
(注:正確に言うと、岡田准一がJ-Waveのラジオ番組中、“行きたい国は?”という質問に、“北欧です”と答え、“インテリアに興味があるんです”と答えていたことによります)。
というように、ずいぶんと市民権を得ている「北欧インテリア」とか「北欧デザイン」なるカテゴリー。ただ、気がかりなのは、その「北欧」にしばしばノルウェーが入っていない?・・・ということです。
イマイチ影がうすい「ノルウェーのデザイン」ですが、「Design Tide in Tokyo 2006」という大きなイベントに、「HEIDU Norway」というタイトルでノルウェーのデザイナーたちが参加。デザイン無知、おしゃれ空間無縁を省みず、Yoko管理人と共に原宿の会場を訪れてみました。
|
|
・・・メイン会場に入るものの、アートな空間に右往左往。3階のHEIDU Norway出展スペースを見つけられたのは、神のご加護によるものでしょう。想像していたのよりこじんまりとした空間でした。じっくり作品を鑑賞する前に、デザイナーたちとお話できる幸運に恵まれ、何となくインタビューが始まります(といっても、専門家ではないので「なんちゃってインタビュー」ですけどね)。
まず初めに言葉を交わしたのは、「StokkeAustad」という2人組のデザインユニット。デザイナーのJonas Ravlo StokkeさんとØystein Austadさんは、まだ若い男性です。
 いつから2人は活動を始めているのですか? いつから2人は活動を始めているのですか?
 2004年にオスロ建築大学の修士を終えたばかりなんだよ。 2004年にオスロ建築大学の修士を終えたばかりなんだよ。
 まだ若いんですね~ まだ若いんですね~
 いや、それほどでも・・・ いや、それほどでも・・・
 日本は初めて? 日本は初めて?
 ああ、初めてだよ。 ああ、初めてだよ。
 今まで、海外で出展など行ったことはありますか? 今まで、海外で出展など行ったことはありますか?
 ミラノ、フランクフルト、ロンドンといったところかな。ミラノの展示会で、日本人関係者の目に留まってね。 ミラノ、フランクフルト、ロンドンといったところかな。ミラノの展示会で、日本人関係者の目に留まってね。
 これからは、日本を含むアジアのマーケットにも興味がありますか? これからは、日本を含むアジアのマーケットにも興味がありますか?
 ありますね。まだ日本以外の国には行ったことがありませんが、ぜひアジアにも作品を紹介していきたいです。 ありますね。まだ日本以外の国には行ったことがありませんが、ぜひアジアにも作品を紹介していきたいです。
 デザインコンセプトを教えていただけますか? デザインコンセプトを教えていただけますか?
 (作品のデスクスタンドを指しながら)シンプルであることを心がけています。無駄なものは取り除いてね。 (作品のデスクスタンドを指しながら)シンプルであることを心がけています。無駄なものは取り除いてね。
 ミニマリズムな作風ですね。 ミニマリズムな作風ですね。
 そうだね。日本のデザインとある種、共通点を感じているよ。シンプル、ミニマリズム、無駄がないところ。 そうだね。日本のデザインとある種、共通点を感じているよ。シンプル、ミニマリズム、無駄がないところ。
 確かにそうですね。 確かにそうですね。
 もっとも日本の製品はもっと、正確さとディテールがすごいと思うけどね。 もっとも日本の製品はもっと、正確さとディテールがすごいと思うけどね。
 日本でも「北欧デザイン」が流行ですが、残念ながら、ノルウェーデザインは影が薄い印象です。それについてはどう感じますか? 日本でも「北欧デザイン」が流行ですが、残念ながら、ノルウェーデザインは影が薄い印象です。それについてはどう感じますか?
 他の北欧諸国に比べて、ノルウェーのデザインは伝統に乏しいかもしれない。でもここ数年でずいぶんと変化が起きている。若くて野心を持ったデザイナーがどんどん登場し、活気のある状況なんだ。 他の北欧諸国に比べて、ノルウェーのデザインは伝統に乏しいかもしれない。でもここ数年でずいぶんと変化が起きている。若くて野心を持ったデザイナーがどんどん登場し、活気のある状況なんだ。
 そういえば、norway says(ノルウェーセイズ)が2年前に来日して展示会を開催した際、会場に足を運びました。でもその場には私しかお客がいなくて・・・。でも今、彼らの人気はすごいですね。 そういえば、norway says(ノルウェーセイズ)が2年前に来日して展示会を開催した際、会場に足を運びました。でもその場には私しかお客がいなくて・・・。でも今、彼らの人気はすごいですね。

 あのMP3プレーヤー(asono mica)がきっかけ? あのMP3プレーヤー(asono mica)がきっかけ?
 はい、そうだと思います。最後に、作品と一緒に写真を撮ってもいいですか? はい、そうだと思います。最後に、作品と一緒に写真を撮ってもいいですか?
 もちろん! もちろん!
気さくに、でも丁寧に応対してくれたStokkeAustadと別れ、次はグラフィックデザイン集団の「Bleed」から、Svein H. LiaさんとDag Solhaugさんが、ミニインタビューに応じてくれました。やはり男性二人組です。
 Bleedのことは、先日、デザインムックで読みましたよ。 Bleedのことは、先日、デザインムックで読みましたよ。
 どの本かな?今、たくさんあって分からないんだ・・・ どの本かな?今、たくさんあって分からないんだ・・・
 Plus 81でした。 Plus 81でした。
 そう?それは嬉しいね。 そう?それは嬉しいね。
 来日は何回目ですか? 来日は何回目ですか?
 僕(スヴァイン)は2回目。 僕(スヴァイン)は2回目。
僕(ダーグ)は初めてだよ。
 作品について教えてください。 作品について教えてください。
 いいよ。 いいよ。
とDagさんが、Sonyの小型液晶ポータブルディスプレイを取り出して、次々と作品を見せてくれました。とてもスマートなプレゼン方法にびっくりです。その中でも目を引いたのが、Bleedが運営するコンセプトショップOneでした。オブジェ、Bleedのロゴをかたどった商品、Tシャツ、あと自転車が置いてあります。
 (会場に置かれた自転車を指差しながら)これは、あの自転車ですね。 (会場に置かれた自転車を指差しながら)これは、あの自転車ですね。
 そう、あの自転車なんだよ。これ以外にも、例えばNRK(ノルウェー国営放送)のラジオ局P3のHP、本のデザイン、あとオスロの“Øya
Music Festival”(夏に開催される野外ライブ)のCDデザインの仕事も手がけてきたんだ。 そう、あの自転車なんだよ。これ以外にも、例えばNRK(ノルウェー国営放送)のラジオ局P3のHP、本のデザイン、あとオスロの“Øya
Music Festival”(夏に開催される野外ライブ)のCDデザインの仕事も手がけてきたんだ。
 日本でも、NRKのP3はネットラジオで聴けるんですよ。 日本でも、NRKのP3はネットラジオで聴けるんですよ。
 本当?それはいいね。 本当?それはいいね。
 デザインの特徴は何でしょう? デザインの特徴は何でしょう?
 シンプルさ、かな。日本のデザインと共通するものを感じるよ。 シンプルさ、かな。日本のデザインと共通するものを感じるよ。
(Sveinさんの手には「無印」の買い物袋がありました)
 日本のマーケットにも興味がありますか? 日本のマーケットにも興味がありますか?
 もちろんあるよ。ただ、ビジネス慣習とかいろいろ違うからね。難しい面があるとは思うよ。 もちろんあるよ。ただ、ビジネス慣習とかいろいろ違うからね。難しい面があるとは思うよ。
 まだ、ノルウェーのデザインは日本で知名度が低いのですが・・・ まだ、ノルウェーのデザインは日本で知名度が低いのですが・・・
 ああ。でもノルウェーでは今、ずいぶん若い世代が育ってきて、変化が起きて面白い状況なんだよ。デザインしてから製品化するまで時間がかかるのが問題だけど、僕たちは、その過程を迅速化するように心がけているんだ。 ああ。でもノルウェーでは今、ずいぶん若い世代が育ってきて、変化が起きて面白い状況なんだよ。デザインしてから製品化するまで時間がかかるのが問題だけど、僕たちは、その過程を迅速化するように心がけているんだ。
 あの可愛らしい自転車と一緒に写真を撮ってもいいですか? あの可愛らしい自転車と一緒に写真を撮ってもいいですか?
 いいよ。 いいよ。
私とYoko管理人は、HEIDU NorwayのTシャツやBleedのバッジをいただきました。Takk!
私たちがHEIDU Norwayのスペースに来てから、段々、お客さんたちが増えてきました。最後に、Charlotte Karlsenさんとお話することができました。唯一の女性デザイナーです。
 作品を見せていただけますか? 作品を見せていただけますか?
 ええ。私はガラス作家なのよ。(シンプルなグラスを指差して)これが私の作品です。 ええ。私はガラス作家なのよ。(シンプルなグラスを指差して)これが私の作品です。
 作品の特徴は? 作品の特徴は?
 そうね。とてもミニマリズムで、機能的なところでしょうか。 そうね。とてもミニマリズムで、機能的なところでしょうか。
 私の日本人の友人は、スウェーデンでガラスを学んだんですよ。 私の日本人の友人は、スウェーデンでガラスを学んだんですよ。
 私も、スウェーデンのコスタボーダでガラスの勉強をしました。それからは、英国で主に活動をしています。 私も、スウェーデンのコスタボーダでガラスの勉強をしました。それからは、英国で主に活動をしています。
 先ほどから、ノルウェー語に英語が混ざっているのはそのせいですか?もしかして、英語の方が簡単? 先ほどから、ノルウェー語に英語が混ざっているのはそのせいですか?もしかして、英語の方が簡単?
 実際、スウェーデンと英国と海外暮らしが長いので、言葉が混乱することがあります。 実際、スウェーデンと英国と海外暮らしが長いので、言葉が混乱することがあります。
 他の作品も見せてください。 他の作品も見せてください。
 私は、仏教に影響を受け、それを作品に生かしているのよ。 私は、仏教に影響を受け、それを作品に生かしているのよ。
 アジアの文化に興味をお持ちなんですね。来日は何回目ですか? アジアの文化に興味をお持ちなんですね。来日は何回目ですか?
 これで4回目です。といっても今までの3回は、英国関係のプロジェクトで来日しました。ノルウェーでの来日は初めてよ。東京はとても魅力的な都市で大好きです。 これで4回目です。といっても今までの3回は、英国関係のプロジェクトで来日しました。ノルウェーでの来日は初めてよ。東京はとても魅力的な都市で大好きです。
 作品と一緒に写真を撮りたいのですが・・・ 作品と一緒に写真を撮りたいのですが・・・
 ええ、いいわよ。 ええ、いいわよ。
とシャルロットさんの写真を撮影したのですが、仕上がりに「う~ん」という感じだったので、もう1枚撮りました。わがまま申して失礼しました・・・。
■インタビューを終えて
さっくり見学する予定だったのですが、予想外のミニインタビューに発展し、デザイナーたちの親しみやすさ、気さくさに触れることができました。
みなさん、良い意味でオプティミストかつ前向きな姿勢が印象的。ノルウェーデザインは、ノルウェー人がそうであるように、マイペースを保って、ゆっくりと日本でも知名度が広がっていくといいな~と思います。

←特選インタビューへ戻る
|
 |
 |
留学生翻訳家イングヴェ・ヨハン・ラーセンさん (06.11.07)
プロフィール
 Yngve Johan Larsen(イングヴェ・ヨハン・ラーセン)さん: 早稲田大学大学院 教育学研究科在学 文部省奨学生 Yngve Johan Larsen(イングヴェ・ヨハン・ラーセン)さん: 早稲田大学大学院 教育学研究科在学 文部省奨学生
現在、日本に何人のノルウェー人留学生がいるのか皆目、見当がつきません。
やはりノルウェー人学生にとって人気の留学先は、英語圏だと思いますが、イングヴェ・ヨハン・ラーセンさんは、2回目の日本留学中。彼は留学生の顔だけでなく、「翻訳家」としても活躍。「バトル・ロワイヤル」(高見広春著、太田出版&幻冬舎)を日本語からノルウェー語に翻訳し、ノルウェーのDamm出版社から発売されました。
ノルウェー語版はなんと608ページ!(こちらをご参照下さい)まさにUtrolig!な翻訳作業だったと想像します。ノルウェー語版”Battle Royale”の翻訳についてお話をうかがいました。
|
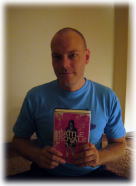
 まず、これほどの大作の翻訳はどれくらいの時間がかかりましたか? まず、これほどの大作の翻訳はどれくらいの時間がかかりましたか?
 1年かかりました。最初のうちは、1日に1~2ページくらいしか進まずスローな出だしだったけど、最後の方は4~5枚のペースにまで上がりました。 1年かかりました。最初のうちは、1日に1~2ページくらいしか進まずスローな出だしだったけど、最後の方は4~5枚のペースにまで上がりました。
 この本を翻訳することになった経緯を教えて下さい。 この本を翻訳することになった経緯を教えて下さい。
 Damm社が翻訳の権利を獲得し、それから翻訳者探しにあたりました。ノルウェーには日本語からノルウェー語に翻訳できる人は少なく、最初は別の翻訳者に聞いたようです。でもスケジュールの関係で断られ、僕に順番がまわってきた。幸い、僕と編集者には共通の知人がいて、会ってからはフレキシブルに事が運びました。“バトル・ロワイヤル”翻訳者の条件として、あまり年寄り過ぎない・・・っていうのも大事だったと思うけど。それから、試訳として10ページを提出し、OKとなりました。 Damm社が翻訳の権利を獲得し、それから翻訳者探しにあたりました。ノルウェーには日本語からノルウェー語に翻訳できる人は少なく、最初は別の翻訳者に聞いたようです。でもスケジュールの関係で断られ、僕に順番がまわってきた。幸い、僕と編集者には共通の知人がいて、会ってからはフレキシブルに事が運びました。“バトル・ロワイヤル”翻訳者の条件として、あまり年寄り過ぎない・・・っていうのも大事だったと思うけど。それから、試訳として10ページを提出し、OKとなりました。
 日本語のスラングとか理解できましたか? 日本語のスラングとか理解できましたか?
 小説版は、とても分かりやすい日本語で書かれています。漫画はすごいスラングが多いけどね。 小説版は、とても分かりやすい日本語で書かれています。漫画はすごいスラングが多いけどね。
 翻訳で難しかった点は何でしょう? 翻訳で難しかった点は何でしょう?
 う~ん・・・日本語とノルウェー語の文章構造の違いによるものかな。例えば、日本語では、主語の省略はしょっちゅうだけど、ノルウェー語は主語が必要。あと、“あなた”とか“お前”といった代名詞は、日本語では使い分けがいろいろあるけど、ノルウェー語では全部、”du”で済んじゃう。あと、ノルウェー語にはあまりない敬語も悩みました。先輩と後輩の会話のシーンとか。 う~ん・・・日本語とノルウェー語の文章構造の違いによるものかな。例えば、日本語では、主語の省略はしょっちゅうだけど、ノルウェー語は主語が必要。あと、“あなた”とか“お前”といった代名詞は、日本語では使い分けがいろいろあるけど、ノルウェー語では全部、”du”で済んじゃう。あと、ノルウェー語にはあまりない敬語も悩みました。先輩と後輩の会話のシーンとか。
 吉本ばななの「キッチン」ノルウェー語版を以前、読みました。日本に特有の単語、“ふとん”(Futon)などを説明する単語帳が本の最初に付いていたのを覚えています。イングヴェさんは、同じような工夫をされましたか? 吉本ばななの「キッチン」ノルウェー語版を以前、読みました。日本に特有の単語、“ふとん”(Futon)などを説明する単語帳が本の最初に付いていたのを覚えています。イングヴェさんは、同じような工夫をされましたか?
 本書では、脚注という形で補足説明を加えました。例えばこのページには、“●●君”(kun)ってどういう意味か入っています。“さん”、”君“、”ちゃん“の意味は全部入れましたよ。あと、“サラリーマン”って単語もノルウェー語にはないから脚注に入れましたね。(思い出したように)、そういえば“大の字で寝る”っていう表現も困りました。漢字の”大“が分からないと、意味が分からないでしょう? 本書では、脚注という形で補足説明を加えました。例えばこのページには、“●●君”(kun)ってどういう意味か入っています。“さん”、”君“、”ちゃん“の意味は全部入れましたよ。あと、“サラリーマン”って単語もノルウェー語にはないから脚注に入れましたね。(思い出したように)、そういえば“大の字で寝る”っていう表現も困りました。漢字の”大“が分からないと、意味が分からないでしょう?
 本当ですね。 本当ですね。
 あと生徒たちが爆弾を作るシーンも大変でした。自分は今まで爆弾を作ったことがないから、専門用語が分からない。後で専門家に単語や表現のチェックをお願いしました。それから、突然、”ロシア式抱擁“(russisk
klem)なんて表現が出てきた時も参りましたね。 あと生徒たちが爆弾を作るシーンも大変でした。自分は今まで爆弾を作ったことがないから、専門用語が分からない。後で専門家に単語や表現のチェックをお願いしました。それから、突然、”ロシア式抱擁“(russisk
klem)なんて表現が出てきた時も参りましたね。
 ??ロシア式抱擁? ??ロシア式抱擁?
 そう、ロシア式抱擁。いきなり出てきて困ったよ。 そう、ロシア式抱擁。いきなり出てきて困ったよ。
 何というか、こんなに分厚い本を翻訳するって本当に大変だと思うのですが・・・・何が完成までに駆り立てたのでしょう。 何というか、こんなに分厚い本を翻訳するって本当に大変だと思うのですが・・・・何が完成までに駆り立てたのでしょう。
 仕事だからね。毎日、翻訳を続けてやり遂げました。あと内容の面白さにも惹かれました。 仕事だからね。毎日、翻訳を続けてやり遂げました。あと内容の面白さにも惹かれました。
 オスロ大学の日本語学科(注:イングヴェさんはオスロ大学東洋文化言語学科修士課程在籍)にノルウェー人学生が増えていると聞いています。アニメとか漫画といった媒体を通じて、ノルウェーでも日本文化に興味を持つ人が増えているのでしょうか? オスロ大学の日本語学科(注:イングヴェさんはオスロ大学東洋文化言語学科修士課程在籍)にノルウェー人学生が増えていると聞いています。アニメとか漫画といった媒体を通じて、ノルウェーでも日本文化に興味を持つ人が増えているのでしょうか?
 確かに、少年ジャンプがノルウェーでも発売されたり、アニメが人気になったりといった傾向がありますが、これはノルウェーだけではなく他のヨーロッパ諸国でも同じ現象でしょう。 確かに、少年ジャンプがノルウェーでも発売されたり、アニメが人気になったりといった傾向がありますが、これはノルウェーだけではなく他のヨーロッパ諸国でも同じ現象でしょう。
 つまり、ノルウェーにもオタクはいるのですね? つまり、ノルウェーにもオタクはいるのですね?
 いますね。日本に行って、漫画をいっぱい読みたいと思っている学生とか・・・ いますね。日本に行って、漫画をいっぱい読みたいと思っている学生とか・・・
 そうした人たちが、この“バトル・ロワイヤル”の読者になるのでしょうか? そうした人たちが、この“バトル・ロワイヤル”の読者になるのでしょうか?
 多分ね。でも、この本は349クローネ(約6000円)もするから、若い子たちには買えないかも。ノルウェーの本は高すぎるよ。まあ物価が高いから、仕方ないけどね。 多分ね。でも、この本は349クローネ(約6000円)もするから、若い子たちには買えないかも。ノルウェーの本は高すぎるよ。まあ物価が高いから、仕方ないけどね。
 本日はありがとうございました。 本日はありがとうございました。
■インタビューを終えて
昨年(2005年)、オスロ大学日本語学科にお邪魔した際に、イングヴェさんは翻訳の話を教えてくれました。その後、ノルウェー大使館のHPで本書発売のニュースを知り、感動。すごい偉業だ~と。怠け者には良い刺激です。
日本語からノルウェー語に翻訳できる貴重な人材として、これからもご活躍を期待しています。個人的には、翻訳が難しそうな町田康、金井美恵子に挑戦して欲しいですね。
←特選インタビューへ戻る
|
 |
 |
ノルウェー大使館 参事官カーリ・ヒルトさん (06.10.21)
プロフィール
 Kari Hirth(カーリ・ヒルト)さん: 駐日ノルウェー王国大使館 文化・報道・広報担当参事官 Kari Hirth(カーリ・ヒルト)さん: 駐日ノルウェー王国大使館 文化・報道・広報担当参事官
東京のノルウェー王国大使館で、参事官として多忙な毎日を送るカーリ・ヒルトさん。カーリさんは2度目の日本赴任で、かなりの「日本通」です。
日本ではまだまだ影の薄いノルウェーについて、積極的にPR役を務め、「ノルウェーについて学ぶサロン」のゲスト講師を快く引き受けて下さいました。講座終了後、お疲れの様子も見せず、私たちのインタビューにも応じて頂きました。
|
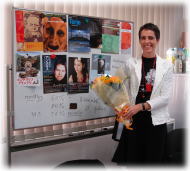
 サロンの感想をお聞かせください。 サロンの感想をお聞かせください。
 とっても素晴らしいイベントでした!日本では、ノルウェーに興味を持っている人は残念ながら少ないです。でも今日、サロンに参加してくださった皆さんはノルウェーに興味を持っている方ばかりですよね。そういう人たちと出会えて楽しかったです(注:受講者の方々のアンケートでも、カーリさんのお話に満足された、というご意見が多かったです) とっても素晴らしいイベントでした!日本では、ノルウェーに興味を持っている人は残念ながら少ないです。でも今日、サロンに参加してくださった皆さんはノルウェーに興味を持っている方ばかりですよね。そういう人たちと出会えて楽しかったです(注:受講者の方々のアンケートでも、カーリさんのお話に満足された、というご意見が多かったです)
 本日は、ノルウェー語レッスンの先生役も務めていただきました。今まで、ノルウェー語を教えた経験はありますか? 本日は、ノルウェー語レッスンの先生役も務めていただきました。今まで、ノルウェー語を教えた経験はありますか?
 自分の夫に15年間もノルウェー語を教えていますよ!(注:カーリさんの夫は、フランス人)ですから、私はノルウェー語を教える“プロ”でしょうね(笑)。夫以外の人にも、教えたことはあります (注:カーリさんは英語・フランス語が堪能。日本語のレッスンも受けています) 自分の夫に15年間もノルウェー語を教えていますよ!(注:カーリさんの夫は、フランス人)ですから、私はノルウェー語を教える“プロ”でしょうね(笑)。夫以外の人にも、教えたことはあります (注:カーリさんは英語・フランス語が堪能。日本語のレッスンも受けています)
 日本で「北欧」というと、やはりスウェーデンのイメージが強いです。それに比べてノルウェーは「目立たない」存在に思えるのですが、そうした現状をどうやって変えていこうとお考えですか? 日本で「北欧」というと、やはりスウェーデンのイメージが強いです。それに比べてノルウェーは「目立たない」存在に思えるのですが、そうした現状をどうやって変えていこうとお考えですか?
 私たちは、ノルウェーの良い面をPRしようと様々な試みをしていますが、まだ十分ではないでしょう。日本には、スウェーデンやデンマーク、フィンランドの企業がノルウェー企業よりたくさんあり、自国製品のPRに熱心ですね。それに比べて、ノルウェー企業の中には、“ノルウェーの会社である”ということ自体が知られていないケースが見受けられます。例えば、ノルウェーの家具は素晴らしい製品がたくさんあるので、もっと多くの人にその良さを知って頂きたいですね。 私たちは、ノルウェーの良い面をPRしようと様々な試みをしていますが、まだ十分ではないでしょう。日本には、スウェーデンやデンマーク、フィンランドの企業がノルウェー企業よりたくさんあり、自国製品のPRに熱心ですね。それに比べて、ノルウェー企業の中には、“ノルウェーの会社である”ということ自体が知られていないケースが見受けられます。例えば、ノルウェーの家具は素晴らしい製品がたくさんあるので、もっと多くの人にその良さを知って頂きたいですね。
 「ノルウェーの労働と休暇」というテーマでお話をして頂きましたが、カーリさんの職務を考えと、平均的ノルウェー人より多く仕事をされているのではないでしょうか? 「ノルウェーの労働と休暇」というテーマでお話をして頂きましたが、カーリさんの職務を考えと、平均的ノルウェー人より多く仕事をされているのではないでしょうか?
 私は、働きすぎです!!5時には帰宅し、子どもたちと過ごすようにしていますが、家でも仕事をしています(注:カーリさんのお宅は大使館から至近なので、5時帰宅が可能なのでしょう) 私は、働きすぎです!!5時には帰宅し、子どもたちと過ごすようにしていますが、家でも仕事をしています(注:カーリさんのお宅は大使館から至近なので、5時帰宅が可能なのでしょう)
 カーリさんが働きすぎ・・・というのは、日本で勤務していることが原因なのでしょうか? カーリさんが働きすぎ・・・というのは、日本で勤務していることが原因なのでしょうか?
 一概にそうとは言えません。今年はイプセンイヤーという大きなイベントがあるので、それが一因でしょう。また、私が勤務する外務省は、昔から長時間仕事をする人が多いですね。ただし、小さな子どもを持つスタッフが働きすぎることは、認められません。 一概にそうとは言えません。今年はイプセンイヤーという大きなイベントがあるので、それが一因でしょう。また、私が勤務する外務省は、昔から長時間仕事をする人が多いですね。ただし、小さな子どもを持つスタッフが働きすぎることは、認められません。
 カーリさんは、今年、夏休みをどれくらい取りましたか? カーリさんは、今年、夏休みをどれくらい取りましたか?
 いい質問ですね!全部で6週間の夏休みをとって、フランスとノルウェーに帰っていました。でも夫の夏休みが2週間しかなかったので、残りの休暇は私一人で子どもの世話や、ノルウェーの身内に不幸があったので、やることがたくさんありました。ちゃんと休んだ気がしませんね・・・・。あと、夏休み以外の休暇は全然取っていません。 いい質問ですね!全部で6週間の夏休みをとって、フランスとノルウェーに帰っていました。でも夫の夏休みが2週間しかなかったので、残りの休暇は私一人で子どもの世話や、ノルウェーの身内に不幸があったので、やることがたくさんありました。ちゃんと休んだ気がしませんね・・・・。あと、夏休み以外の休暇は全然取っていません。
 日本での生活には満足していますか? 日本での生活には満足していますか?
 ええ。とっても! ええ。とっても!
カーリさんと別れる間際、「今日のサロンで言い忘れたことがあった!」と叫び、ご自分が穿いている黒いスカートを見せてくれました。ノルウェー人デザイナーの作品で、とても可愛いらしいポケットが印象的。カーリさんのために作ったスカートで、世界に一つしかない貴重なものを見せて頂きました。
 本日は本当にありがとうございました。Tusen takk! 本日は本当にありがとうございました。Tusen takk!
■サロンとインタビューを終えて
私は原稿がない講演通訳をするので、サロンの日が近づくにつれ緊張が高まっていました。
そして当日。カーリさんと待ち合わせ場所、JR田町駅改札に向かうと、彼女はおにぎりを食べながら立っていました。その姿をみて、緊張がみるみる解けていくのが分かりました・・・。カーリさんの「外交戦略」と言えるでしょうか?
カーリさんは、いつ会ってもエネルギッシュで前向きです。たくさんのイベントを企画し、ノルウェーから様々なゲストを迎え、ノルウェー人と日本人、ノルウェーに興味を持つ日本人同士のネットワーク作りに、取り組まれています。
現状に満足せず、常に「もっと良いもの」を求め、サロンでは何度も参加者の皆さんに、「大使館のHPに、何か意見やリクエストがあれば、たとえネガティブなものであっても、気軽にメールを送って下さい」と呼びかけている姿が印象的でした。
これからも、ノルウェー大使館が催すイベントを楽しみにしています。
「ノルウェーについて学ぶサロン」レポート(第7回)
■参考URL
ノルウェー大使館 http://www.norway.or.jp/
←特選インタビューへ戻る
|
|


|