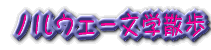

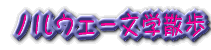

2001年5月17日(ノルウェーの憲法記念日)、北欧樂会(がっかい)主催、(財)東京市町村自治調査会多摩交流センター助成事業のご協力を得て、国分寺Lホールにて、「ノルウェー文学散歩」というタイトルで講演を行いました。
講師は、当サイトの発行責任者であるAokiです。当日は、新旧取り混ぜた4つの文学作品を紹介しました。
講演サマリー
●はじめに−400年間の暗闇と100年間の暗闇
去年の夏、オスロ大学の留学を終えて帰国してから、2回ほど文学に関するテーマでお話しする機会がありましたが、その度に、北欧文学、更に言えばノルウェー文学を語る難しさを実感しています。というのも、アメリカ文学、フランス文学のように「メジャー」なジャンルであれば、講師と観客の共有する知識というものが、ある程度、期待できますが、こと「ノルウェー文学」を話す立場にとっては、果たして観客の皆さんが、どれだけの知識をお持ちであるかは、未知数でありますし、聞き手の立場からすると、「延々2時間も、訳のわからない作家の話を聞かされた」と、「楽しむ会」どころか「苦しむ会」になりかねません。
しかし、今は冷遇されている「北欧文学」は、明治・大正時代の芸術家・文化人にとって、必須の「教養」でした。鴎外の翻訳によるイプセンの戯曲を、帝劇で初めて上演した時の熱気を、鴎外の娘、森茉莉はエッセイにしたためていますが、それを読むと、当時、北欧文学とは堂々たる「メジャー」であったことがわかります。
では、どうしてこの熱気は、日本で続かなかったのでしょうか?原因は様々でしょうが、やはり「北欧語」という言葉の壁、研究機関・研究者の圧倒的な不足などが、大きな原因でしょう。日本には、多すぎるほど大学がありますが、ノルウェー語・文学を専攻できるのは、わずか1校だけです。
イプセンの戯曲「ペール・ギュント」の中に「400年間の暗闇」という表現があります。これはノルウェーが、14世紀から19世紀のデンマークの連合下におかれた間、ノルウェーの文化・芸術が停滞し、ほとんど空白になってしまった時代を表す表現です。
以前、私が住んでいた町の図書館に行った時、ノルウェーの作品として並んでいたのが、「人形の家」と「ソフィーの世界」だけでした。これは、日本におけるノルウェー文学の状況を、象徴していると思います。19世紀と20世紀、両作品の間には、「100年間の暗闇」が横たわっています。
今日の講演で、本来ならまず、ノルウェーの文学史を、きちんとご説明したいのは山々ですが、時間の制限がありますので、私が好きな作品、ぜひ紹介したいと思う作品を、気ままにお話しさせていただく内容にしました。幸い、タイトルも「散歩」ですから、逸脱・脱線もお許し頂きたいと思います。
●ヘンリック・イプセン「ヘッダ・ガブラー」(Henrik Ibsen, Hedda Gabler, 1890)
「またイプセン?」とか、「それしかないの?」と言われると辛いですね。知ってるようで意外と知らない、イプセンの略歴をお話ししましょう。
1828年、南ノルウェーのシーエンに生まれる。実家は富裕な商家だったが、イプセンがまだ幼い頃、家業が傾き没落。15歳で自立してから、妹以外の家族全員と縁を切ってしまいます。23歳の時、ベルゲンの劇場付作者兼舞台監督を務めるが、上演しても失敗作が多く不遇の時代が続きます。36歳から外国に渡り、以降27年間、外国生活(ドイツ、イタリアなど)を送ります。
1866年「ブラン」が成功。67年には「ペール・ギュント」を発表。そして、1879年には「人形の家」、84年には「野鴨」、90年に「ヘッダ・ガブラー」。91年にノルウェーに帰国し、亡くなったのは1906年。国葬が行われました。
イプセンが「人形の家」を書いた時は、すでに51歳になっていましたら、遅咲きの芸術家と言えるでしょう。「イプセン戯曲選集」(毛利三彌、東海大学出版会)によると、当時、劇場付でなければ劇作家が生活を維持するのは難しかったそうですが、イプセンのように定職につかず、パトロンを持たず、劇作のみを書きつづけ、しかも2年に1作のペースしか発表しなかったのにも関わらず、晩年にはノルウェー有数の金持ちになっていたことは、非常に珍しいことだそうです。
この「ヘッダ・ガブラー」は、「人形の家」ほど知名度のない作品ですが、イプセンのお芝居の中では、「人形の家」のノーラに並んで、ヘッダは、女優にとって演じたい役だと、ノルウェー人から聞きました。
確かに、大学の講義で「ヘッダ・ガブラー」が取り上げられた際も、クラスの反応は良かったです。ただその時、わずか1人しかいなかった男子学生(イギリス人)は、主人公ヘッダのことを、英語で「bitch」と表現し、それに対して、圧倒的多数の女子学生たちは、「そんなことない!」と猛反発したことが、印象的でした。
家を捨てたノーラが、当時の人々の反発を買ったように、ヘッダは、作品発表当時から、「悪魔的、破壊的な女性」とみなされ、作品自体も、あまり評価されませんでした。例えば、イプセン、ビョルンセンなどノルウェーの作家に多大な影響をもたらした、デンマークの文芸評論家ゲオルグ・ブランデスは、「ヘッダは、卑しく愚かであり、興味がわかない」と、切り捨てています。主人公ヘッダには、確かにアンチ・ヒロイン的要素が、備わっています。まとめてみましょう。
こうした「悪魔的」なヘッダの評価を変えた本として、良く知られているのが、ノルウェー人の文芸評論家エルセ・フストの博士論文「ヘッダ・ガブラー」(1958年)です。それ以降、「ヘッダ・ガブラー」の再研究・再評価が盛んになり、ヘッダを単なる「悪女」で終わらせることなく、様々な分析が試みられるようになりました。
まず、ヘッダに才気があることは明白でしたが、そうした才気を生かし、仕事を得るなど自己実現を図ることは、当時の上流階級の女性にとって不可能であり、彼女は、ただ人生を無為に過ごすことしかできません。関連したシーンを引用しましょう。ヘッダが、ブラック判事と2人で会話しているシーンで、この時、ヘッダは、テスマンとの新生活に対する不満をもらしています。
へ:ああ判事さん−わたし、今にここで恐ろしく退屈してくるんでしょうね。
ブ:あなたの人生にも、何かすべき仕事はあるんじゃないですか、ヘッダさん?
へ:仕事−熱中できる?
ブ:できればね。
へ:一体どんな仕事。私はよく考えましたけど−(いえ)それもだめ。
ブ:どうして?言ってごらんなさい。
ヘ:テスマンを政界に送りこめたら。
ブ:テスマンを!いやいや−政治なんてのは全然むいてませんよ。(「イプセン戯曲選集」、毛利三彌訳、東海大学出版会)
ヘッダのセリフから、自分でなく夫を通して、目的を果たそうとする姿勢が読み取れますが、これは、当時の社会の限界をあらわしているでしょう。
また「強い女性」と思われがちなヘッダですが、妥協した結婚を選んで、凡庸なテスマンの夫人になります。自ら、「スキャンダルがこわい」と告白しているように、ヘッダは、属する階級の規範やモラルにがんじがらめになっていて、それを打ち破る勇気はありません。
「人はそんなことをしないものよ」が彼女の口癖ですが、最後の自殺で初めて、世間の決まりごとを破ったヘッダに、呆然としたブラック判事は、「人はそんなことをしないものだ!」とつぶやきます。
「人間の運命は、その生まれと環境によって決まっていて、変えられない」という自然主義文学の法則が、この作品には当てはまるかもしれません。いわば、ヘッダは彼女を取り巻く「環境の犠牲者」であり、「死」でもってしか自分を縛る物から逃れることはできませんでした。
戯曲の重要人物であるレェーヴボルグとヘッダの関係も、ミステリアスです。
ヘッダは、ボヘミアン的生き方をしていた、レェーヴボルグに特別な感情を抱き、彼を通して、自分には手の届かない、見知らぬ世界に憧れていました。彼こそが、彼女の夢見る美しい世界の体現者であったはずなのに、エルヴステード夫人の助けを借りて、再び世間と折り合いをつけ、「まとも」に生きようとした彼に失望したことは、想像に難くありません。
さらに、元愛人の家で下腹部を撃たれて死んでしまった彼の死にざまは、彼女の美意識も夢も大きく裏切りました。レェーヴボルグは、潔く自殺したと信じこんでいたヘッダに対して、ブラック判事が、真相を告げるシーンから引用します。
へ:(略)わたしにわかっているのは、エイレント・レェーヴボルグが自分の思いとおりに人生を生きる勇気をもっていたということだけ。偉大よ!美しい!あの人にはこの人生を絶つだけの力と意志があったのよ−こんなにも早く。
ブ:大変心苦しいんですがね、ヘッダさん−私はあなたの美しい幻想を破らざるを得ないんですよ。
(略:ブラックは、レェーヴボルグが元愛人の化粧部屋で死んだことを告げる)。
ブ:レェーヴボルグの胸のポケットに入っていたピストルが発砲されていた。その玉が致命傷だったんです。
へ:胸に当たってーええ。
ブ:いいえ−当たったのは下腹部でした。
ヘ:(嫌悪の表情で)ああ、それもなの!私が手に触れるものは何もかも、こっけいで低俗なものになってしまう。そういう呪いにかかっている。
日本における「ヘッダ・ガブラー」の評価について、触れてみましょう。
文芸評論家でもあり、「ヘッダ・ガブラー」の翻訳および、演出を手がけた福田恆存の著作に興味深い指摘があります。先ほど、「ヘッダ・ガブラー」発表当時の悪評について申し上げましたが、そうしたヨーロッパでの悪評とは対照的に、「小説神髄」で知られる坪内逍遥は、「ヘッダ・ガブラー」を高く評価し、主人公を矛盾した新しい女とみながら、「マクベス夫人の如き異常な人物と考えるのは誤り」と記したそうです。逍遥の卓越した批評眼がうかがえます。
「社会問題劇」と評されることが多いイプセンの作品ですが、作者自身は、この「ヘッダ・ガブラー」について、「問題を描くのではなく、人間を描きたかった。語っているのは登場人物であり、私ではない」と言っています。
実際、主人公ヘッダの複雑で屈折した性格設定を始め、彼女が感じる人生への焦燥感、失望感、虚無感を描き切った、イプセンの筆力は素晴らしいと思います。
家を出てしまったノーラは、確かに勇気があり大胆でした。ヘッダにはそんな勇気もなく、家を出ることなど考えられません。しかし、「人形の家」のノーラより、ヘッダの方が、より現実的で生身の人間に私は感じます。彼女の人生に対する絶望感、虚無感は、時代を超えて、心を打つものがあるからかもしれません。
●タリエイ・ヴェーソース「鳥」(Tarjei Vesaas, "Fuglane" 1957)
日本では、ほとんど知られていないタリエイ・ヴェーソースは、ノルウェーを代表する作家のひとりです。経歴を簡単にお話ししましょう。
1897年に、テレマルク地方に生まれる。実家は、農家で彼は跡取息子。フィヨルド観光で有名なヴォスのフォルケホイスコーレ(国民高等学校)に通った。父親が読書好きだった影響で、彼も家でたくさんの本を読み、作家になることを夢見、そして、農園を継がず、作家の道を選ぶ。しかし、初期の作品は読者が少なく、批評も否定的だった。
1940年に発表した「胚種」(Kimen)で、ようやく注目を集める。その後、「暗闇の中の家」(Huset i mørket、1945)、57年の「鳥」、63年の「氷の城」(Is−slottet)が主な代表作。
妻のハルディス・モーレン・ヴェーソースは、著名な詩人。彼女の詩は、3月に行った立川市の講演会で紹介しました。
ヴェーソースは、ニーノシュクの作家。ニーノシュクについて簡単に説明すると、ノルウェーには、ブークモールとニーノシュクという2つの書き言葉があるが、ニーノシュクは、全人口のうち15%くらいの使用人口。
彼の作品を、「ニーノシュクだから」という理由で、敬遠するノルウェー人がいるのは残念。現に私は、留学時に、この「鳥」を講義で読んでいる、とノルウェー人の友人に話したら、「そんなもの読まなきゃいけないなんて、かわいそう」と言われたほどです。
確かに、私自身も、ニーノシュクで読みにくいと、最初は抵抗があったが、読み進めるにつれ、作品のユニークさ、素晴らしさに心惹かれ、徐々にニーノシュクは、気にならなくなりました。
本書を読んだことがある方はいないようなので、簡単にあらすじを説明します。
(あらすじ)
主人公マティスは、37歳。姉ヘーゲと二人暮らし。マティスは、普通に働いたり、人とコミュニケーションする能力が欠けているが、自然に対する鋭く原始的な感覚や、内面に素晴らしい詩的感覚をもっている。村人たちは、彼を「間抜け」と呼んでいるが、彼自身は、自分が他人からどう見られているかといった自己認識を、人々が想像する以上に備えている。
姉ヘーゲは、弟の代わりに家計を支え、彼に対する扶養義務を負っているが、生活に疲れ、「自分がどうして存在するのかわからない」と、常に満たされない思いで生きている。
ある日、2人に家の屋根にヤマシギが飛んできて、マティスはそれ以来、鳥と「鳥の言葉」を通じてコミュニケーションをはかり、どんどん鳥と自分を同一化させていくが、結局、鳥はある少年によって撃ち殺されてしまう。マティスはショックを受けるが、ヘーゲの言う通り、土の中に埋める。村にある2本の寄り添った木を村人達は「マティスとヘーゲ」と名付けていたが、その木の1本が雷によって倒れてしまった時も、マティスは、木と自分を同一化するあまり、自分かヘーゲかどちらかが死ぬのでは、とおびえてしまう。
マティスは、単純な肉体労働を嫌って、最後までやり遂げられないが、湖でボートを漕ぐことは好き。ヘーゲは、森の中の湖で船頭をやってみれば、とマティスに勧め、彼は張り切って仕事を始める。ただ、湖の対岸には家がないので、お客はなかなか来ないが、やっと来た最初の客が、木こりのヨルゲン。マティスは彼を自分の家に連れて行き、それから3人の生活が始まる。
ヨルゲンの出現により、マティスとヘーゲの生活は変化する。お互いに惹かれあうヘーゲとヨルゲン。ヘーゲに捨てられるのでは、と常に怖れていたマティスは、「これからも今まで通り暮らそう」というヘーゲの言葉に安心できない。死んで行った鳥に自分の運命をみるマティス。そして、彼は、死を覚悟したある賭けに似た計画を実行するため、湖にボートで出かける...。
印象的な主人公、マティスについて取り上げましょう。
作者のヴェーソースは、主人公マティスに愛着があったようで、「主人公と作者の間には、親密な友情があった」とエッセイで述べています。「間抜け」と呼ばれるマティスに関するアイディアは、すでにヴェーソースの頭には、戦前からありましたが、戦後、1952年にまず、「間抜け」というタイトルの短編で、マティスとヘーゲ姉弟を登場させています。
この短編のマティスは、「鳥」のマティスと同じように、普通に働いたり、人とコミュニケーションすることがうまくできません。ある日、思いがけず、木こりの仕事を得ますが、切り倒される木に自分の運命をみた彼は、木こりとしての仕事を果たせません。「鳥」のマティス同様、自然との強い同一化の様子が描かれています。この短編を更に発展させて、「鳥」が生まれました。
「鳥」の主人公マティスの存在は、様々な捉え方が可能です。彼は、普通の人のように仕事ができません。いわば、「社会の役立たず」とみなされていますが、彼の存在は、現代の効率的社会に対する作者の静かな抗議と受け取れます。例えば、マティスが、カブ畑の種まきを手伝う仕事を得た時、農園の主に対して、「こんなにたくさんのカブを一体、どうするの?」と聞くシーンがありますが、主は、答えられません。きっとそんなことを考えたこともないのでしょう。マティスの問いは、とても根源的で、社会の基盤前提を揺り動かしかねません。短編「間抜け」のマティスも、木を切る時、「こんな木を切らなくちゃいけないなんて残念だな」と考えてしまいます。
また、作者自身は、マティスを「よるべのない詩人」と表現しました。マティスは、自然の中の小さな物にまで、鋭い感覚を持ち、彼の内面は、詩的表現に満ちています。
しかし、そうした豊かな内面を、他人に表現する能力が欠けているので、マティスの心の動きがわからない周囲の人々は、突然発せられる言葉に驚き、戸惑い、時には不安を覚えるようになります。
マティスとヘーゲの家の屋根に、鳥がやって来てから、彼の心は、鳥のことで一杯です。だから、彼は、ヘーゲや、カブ畑で会った女の子、商人など会う人ごとに、鳥のことを話さずにはいられませんが、その鳥が、マティスにとってどれだけの意味を持っているかを理解できる人はいません。
他の場面から例を挙げると、2本の寄り添って立っている木は、「マティスとヘーゲ」と村人から呼ばれていましたが、その木の1本が、雷で倒されしまったのを見たマティスは、自分かヘーゲのどちらかが死んでしまうのでは、死の予兆なのでは、とおびえます。そして、死んでしまうのはどちらなのかを考え続け、木が見える場所で、通りすがりの男に以下のように訊ねます。
マ:「雷のせいで、片一方の木がどうなったか見える?」
お:「ああ、ひどいね」
マ:「でも、あれは誰かな?」
お:「もう言っている意味がわからない」
マティスの心の動きがわかる読者には、当然、彼の問いかけの意味がわかります。が、会話の相手にはマティスの問いかけは不可解で、その背景に深い意味があることは分かりません。
更に、マティスがなぜ、人とうまくコミュニケーションできないか、を考察してみましょう。
マティスは、人が聞きたくないことや真実を、率直に尋ねたり、言ってしまう傾向があります。世間の会話のルールを踏み外してしまうのです。
例を挙げると、カブ畑農園の親切な妻に、姉へーゲの苦労を語るシーンがあります。
マティス:「ヘーゲは今では髪の毛が白髪になってしまった。僕がいるのは、いいことじゃないんだ」。
これは真実ですが、人々が「聞きたくない」真実です。困った妻は、「黙ってちょうだい」と言いますが、マティスはさらに質問を続けます。「どうして、こうなんだろう?」と。妻は頭を振って、答えられません。人生の不条理をも感じさせるこの重い質問は、「誰にも答えられないだろう」と作者は言っています。この答えを探して、マティスはさまよいます。
作者のヴェーソースは、マティスに愛着と友情を感じていたと先ほど述べました。実際、2人には共通点があります。ボートを漕ぐ事が好きなこと、多弁でないこと、詩的感覚に優れていることなどが挙げられるでしょう。
エッセイの中で作者は、次のように語っています;「たくさんの読者が私に、マティスを自分のことのように感じる、と言ってきた」。
私自身も、留学中、ノルウェーに暮らす外国人という立場で、マティスを近しく感じました。私の使うノルウェー語は、表現力、正確さにおいて限界がありました。人と話していて、もどかしく感じたことは、多々あります。ただ、言葉が不自由だからと言って、私が何も感じないとか、理解していない、ということではありません。いわば、内面や体つきは大人なのに、コミュニケーション能力だけは子供、というギャップに悩んでいました。
マティスが、よく使うフレーズに「僕とヤマシギ、のような」(Eg og rugda liksom)があります。彼が、自分と鳥との特別な関係を表現している時に、出てくるフレーズのようですが、周りの人間には、理解できません。このノルウェー語、liksomは、「〜と同じように」とか「〜のように」などという意味ですが、マティスは、自分の表現力に余る部分を、よくこの単語に置き換えて使っています。
感情を伝え切れないマティスのもどかしさが、この言葉に、にじみ出ていますが、liksomは、同時に、外国人が多用する単語としても、知られています。微妙なニュアンスを表現できないモヤモヤを、liksomという単語に置き換えてしまう点で、私には、マティスの悲しみが理解できました。
この「鳥」は、ヴェーソースの生前、ポーランドで映画化され、ノルウェーでは1968年に公開されました(監督:Witold
Leszcynski)。
ヴェーソース自身、マティスを演じた俳優(Franciszek
Pieczko)や、映画全体の出来ばえに満足したようですが、原作とはやや異なる唐突なラストシーンだけは、異議を唱えました。私も、大学の講義で、この映画を見ましたが、主人公マティス役の俳優の演技に感動しました。演技にわざとらしさがなく、ごく自然に、「大きな子供で、よるべのない詩人」マティスになりきっていたのです。
●オスロの街を舞台にした作品
イプセン、ヴェーソースとノルウェーを代表する作家たちの作品を、紹介しましたが、これからは、現代ノルウェーを代表する人気作家ふたり、ラーシュ・ソービエ・クリステンセンとトーベ・ニルセンの小説について、お話ししたいと思います。
まず、2人の作品の、共通点に触れてみましょう。作品の文体ですが、スラングを多用した口語体です。また文章は短く、リズム感があります。そして、作品の舞台は、両作家ともオスロ生まれで、自分が育った地区を舞台にする事が多いです。
これから挙げる作品は、講義で読んだものではありませんが、好きな作品なので紹介したいと思います。
●ラーシュ・ソービエ・クリステンセン「アマチュア」(Lars Saabye Christensen,"Amatøren"
1977)
作者の経歴ですが、クリステンセンは、1953年オスロ生まれ。この小説「アマチュア」が、デビュー小説。その後、勢力的に作品を発表。ビートルズに憧れる青年たちを描いた「ビートルズ」(Beatles,1984)は、80年代、最もヒットした文学作品の1つ。また、小説「ハルマン」(Herman,1988)は、映画化もされた。主人公ハルマン少年は、髪の毛を失うという悲惨な体験をしながらも、得意のユーモア、機転とへらず口で自分の世界を守り抜きます。小説以外にも短編集、詩集を出し、その他、ラジオ、テレビドラマの脚本なども手がける多作な人。
不思議なことに、彼の作品を嫌いだというノルウェー人には、まだ会ったことがありません。国民的作家と言えるでしょうか。
個人的なエピソードとしては、去年の夏、オスロの本屋で、彼を見つけ、恥をしのんで話しかけ、サインをもらうことに成功しました(髪型が特徴的なのでわかりやすかった)。少し、話しをしましたが、作品同様、気さくな人でした。
さて、この「アマチュア」の主人公は、クリスチャンという名のオスロ大学の学生。彼は、勉強に興味が持てず、講義中に居眠りしたり、また当時、大学で盛んだった学生運動にも関心はありません。だからといって、ブルジョワ階級に属する自分の家族に親しみを覚えるわけでもありません。将来のプランや人生の目標もない、と「ないない」づくしのアンチ・ヒーロ的主人公の失敗続きのエピソードを、スラングを多用した簡潔な話し言葉で、作者はユーモラスに語ります。
オスロ大学留学時、文学の先生が、70年代当時の大学の様子を語ってくれた時がありました。当時、大学内でしばしば学生集会が開かれて、会場は、左と右、それぞれ支持する学生が、きれいに分かれ座っていて、真中に座ることは、許されない雰囲気だったそうです。
それが当時の風潮であったとすれば、主人公クリスチャンのように、左にも右にも関心がなく、属そうとしない人物を主人公にした作品を発表したのは、作者の冒険だったと言えるでしょう。しかし、この作品は、特に若い読者から、好意的に受け入れられました。
私なりに原因を想像して、関連する箇所を一部を引用してみましょう。クリスチャンとは対照的に、学生運動にも講義にも熱心なエルセという学生に対する、主人公クリスチァンのモノローグから;
「俺には、何かをちゃんと信じるという才能がないんだ。エルセは、大多数の人間と同じ考えを選択して、それをしっかり信じこんでいる。そして、その思想の中で、気持ち良く浸かっているんだ(中略)。でも俺は。俺は、何かを信じる人間や思想なんてものには、とんでもなく疑い深くなってしまう」。
今の引用からも分かるように、彼は、何かを盲信する人間や行為に対する強い違和感と疑問を抱いています。そして、彼の家族が代表するブルジョワ社会にも、学生たちの左翼的環境にも安らぎを得られず、笑いであるとかブラックユーモア的な批評を武器に、周囲に対して、かろうじて自分を守っています。
また、例を挙げると、クリスチャンが小さい頃、学校が一緒だった金持ちの俗物ボリスと、久しぶりに大学のバーで再会したシーンがあります。少し補足説明をしたいのですが、英語の表現で「you
know」がありますね。アメリカのドラマや映画を見ていると、本当によく使われているなーと思う表現ですが、ノルウェー語では、「vet du」と言いまして、直訳すると「知っているだろう」。
ボリスは、短い会話の中に、3回も「vet du」を連発して、それに対してクリスチァンは、意地悪く、「俺は知らないよ」と言い返しています。その後の彼のモノローグで、「いつもいつも『vet du, vet du』と言っているヤツほど最悪なものはない」と言っていますが、思わず、主人公に賛成!という気持ちで、喝采したくなりました。
こうした彼の生き方や感覚は、当時の学生を始めとする読者たちに、新鮮に映ったのではないでしょうか?「こんな生き方でもいいんだ」というように違う選択肢を示したのだと思います。
若い学生たちに、ラーシュ・ソービエ・クリステンセンが、支持されているエピソードを1つ挙げましょう。
主人公クリスチァンが住んでいた設定のオスロの学生寮(Sognstudenthjem)は実存しますが、この学生寮にあるバーは、小説のタイトルから名前を取って「Amatøren」という店名になっています。
作品の舞台にもふれてみましょう。ラーシュ・ソービエ・クリステンセンは、しばしば、オスロの西側マヨースチューエンやフログネル(ヴィーゲラン/フログネル公園の近く)を、舞台に選んでいます。本来、西オスロのこの一帯は、「高級住宅地」として知られていますが、作品で使われているスラングや、気取らない話し言葉の影響からでしょうか、彼の作品から受けるこの地区の印象は、「高級住宅地」とはトーンが異なります。
今年の秋には、次回作が予定されているようですが、次回作が楽しみな作家のひとりです。
●トーベ・ニルセン「摩天楼の天使」(Tove Nilsen,"Skyskraperengler" 1982)
トーベ・ニルセンは、1952年、オスロ生まれ。70年代に当時、盛り上がりをみせた「社会主義的な作風の女性文学」の書き手として、デビュー。中絶や同性愛といった問題を取り上げました。80,90年代になると、テーマ、語り口ともに広がりをみせ、とりわけ移民問題を積極的にテーマに選んでいます。現在でも、活発にマスメディアに登場し、昨年の夏には、新聞紙上で繰り広げられる作家・文芸評論家の議論の場に、どうして女性作家や評論家は積極的に参加しないのか、と投稿し、一石を投じました。
これからご紹介する「摩天楼の天使」(1982)は、作品評価もさることながら、多くの読者を獲得した本としても、知られています。10万部以上が売れたそうですが、これは人口400万のノルウェーでは、「大ヒット」の部類でしょう。
ニルセンは、14年後の1996年に続編「摩天楼の夏」、97年には更に「ゲオルグのG」を発表。このシリーズは3部作になりました。
「摩天楼の天使」の舞台は、「アマチュア」と同じ、オスロ市内ですが、もっと東側の新興住宅地を舞台にしています。作者自身が育ったBølerという地区は、50年代の終わりに、ノルウェーでは当時、珍しい高層の集合住宅が建設されました。
ノルウェーの各地から、この新興住宅地に引っ越してきた人々の様子を、主人公の少女の目を通してエピソード形式で描かれます。
主人公の名前は、トーベといって、まさしく作家と同じ名前です。本作のトーベは11歳で、夢は作家になること。物語の語り口は、まるで作家トーベ・ニルセン自身が、11歳の少女に再び戻ったかのような調子です。
主人公トーベの視線は、自分を取り巻く同世代の子供たちと、大人たち両方にそそがれます。子供たちの描写では、互いの仲間意識、友情といったもの以外にも、子供の持つ残酷さ、様々な好奇心、いたずら、性に対する興味などが綴られます。
トーベは、両親が本棚の奥のほうに隠している大衆恋愛小説を見つけだしては、部屋でこっそり読みふけっていますが、一方、隣室では、彼女の両親が声をひそめて喧嘩している様子が、パラレルに語られるシーンがあります。両親たちは、深刻な状況でありながら、大衆恋愛小説からの引用の効果もあって、全体的には、ユーモラスな印象を与えます。
こうした大人と子供の様子を、パラレルに語るシーンは他にもあります。大人たちが、「共産主義の脅威」を熱心に話し合っている一方、子供たちは、ソフィア・ローレン、ジーナ・ロロブリジーナ、グレース・ケリーのうち誰が一番の女優かを、かたわらで同じように熱心に言い合っている様は、大人・子供双方が真面目に語り合っている分、滑稽味が増します。
また、この高層団地にはたくさんの住人がいますから、当然、変わっている人もいます。
子供たちはそうした人々を見過ごしません。貧しい人、隣人と一切付き合わない人、ソビエトに憧れている若い青年など、主人公トーベの視線はそそがれます。例を挙げましょう。住人の1人、ある男性は妻に去られてから、隣人とも全く付き合わず、常に書類かばんを大事に抱え行動し、大人・子供両方の憶測を呼びます。ある日、トーベは、彼とエレベータで乗りあわせた際、思いもかけず、彼と言葉を交わします。そのシーンから;
男:いくつになるの、お嬢ちゃん。
ト:10月に12歳になる、と短く答える。「あたしはもうお嬢ちゃんじゃない」
男:11歳。すばらしい年だ。美しくけがれのない時代。素晴らしい年月はすぐに過ぎてしまうのは残念だ。すぐに過ぎてしまい、やがて大人になってしまう。
彼は、肩を震わし、悲しそうに微笑んだ。
その後、男はマンションから飛び降り自殺をしてしまいます。ミステリアスだった彼の謎は結局、解明されませんが、トーベとの短いやりとりから、彼の人生を一瞬、垣間見ることができます。
作家トーベ・ニルセンを「視線の作家」という形容がありますが、彼女の視線は、つねに未知なるもの対するあくなき好奇心に支えられているでしょう。
すぐれた作品の多くがそうであるように、「摩天楼の天使」は、様々な楽しみ方が可能です。物語の面白さ以外にも、当時の風俗や習慣を知ることもできますし、また普通の人々が実際にどのような言葉で会話しているのか、うかがい知ることが出来ます。
風俗に関して言えば、オスロ近郊のドランメンという町に「世界一の大女」がやって来た、という宣伝につられて、家族みんなで見世物小屋見物に行く様子が語られています。また、主人公トーベの家にロシア人の船乗りたちがやって来た様子の描写から、当時のノルウェーでは「外国人」は、まだまだ珍しい存在であったことがわかります。
更に、この高層団地の存在に対する世間の捉え方も興味深いです。マスコミが、「あそこは、若者の犯罪が多く、住んでいる子供は想像力をなくす」など否定的に報道した様子が文中、引用されていますが、新しい物に対する否定的な見解は、日本もノルウェーも変わりませんね。
最後に、作品に使われた言葉使いに触れてみましょう。L.S.Christensen同様、トーベ・ニルセンは「話し言葉」の名手。Christensenより更に、くずしたラディカルな「オスロ方言」を多用しています。文章は短く簡潔ですが、方言解読は、外国人読者にとっては難しいです。ノルウェー語の教材テキストとは、かなり異なるノルウェー語ですが、この言葉使いがあるからこそ、作品が生き生きと血の通ったものになっているのでしょう。
ニルセンの言葉使いはラディカルですが、彼女の語る物語は、プロットや出来事、生き生きとした人間描写などを備えた伝統的な手法によるものです。
●おわりに
年代も作風も異なる作家4人を、取り上げた講演会。皆さんにとって、初めて聞く作家の名前もあったと思います。今日の主眼は、「人形の家」と「ソフィーの世界」以外にも、ノルウェーには素晴らしい文学作品がある、ということを知っていただきたいという、シンプルなものでした。
先日、ノルウェーの国王夫妻が来日された際、早稲田大学が国王に名誉博士号を贈りましたが、その記念式典で、早稲田の総長が、ノルウェーと日本、早稲田大学の文化的結びつきの強さを強調し、イプセン、ムンク、グリーグなどの名前を挙げましたが、いずれも前々世紀に活躍した人物ばかりで、もっと新しい人の名前が聞きたかった私は、残念に思いました。
全く知らない外国語を見ても、それは意味のない文字の羅列に過ぎませんが、その言葉が理解できるようになると、意味のない文字の羅列は、命を得るようになります。
遠く離れたノルウェー語と日本語、文化や歴史など様々な違いを越え、ノルウェーの文学に接し、少しでも作者の声に触れられたと感じた時、「ノルウェー語を学んで良かった」という気持ちになれます。
今日挙げた作品は、「ヘッダ・ガブラー」以外、邦訳されていませんが、観客の皆さんの中で、「作品を読んでみたいから、ノルウェー語を勉強してみよう」と思っていただければ、教える立場の者としてこんなに嬉しいことはありません!